|
<武田氏の祖は誰か?>
黒澤明の映画「影武者」で、信玄の死後勝頼が長篠の設楽ヶ原へ出陣する途中家臣たちがその出陣を止めようとしたとき、「我が武田は新羅三郎義光公以来、敵に後ろをみせたためしは無い!」といって強引に兵を進めるシーンがあるが、ここに出てくる新羅三郎義光という人物が武田家の先祖といわれていることは有名である。この新羅三郎義光という人は、三郎という名の通り源頼義の三男である。ちなみに長男は八幡太郎義家である。
源氏と甲斐の国との係わり合いは、この頼義の父である頼信が甲斐守になったことから始まる。当時房総半島で起きた平忠常の乱を鎮定することになったのである。結局平忠常は頼信に降伏し頼信は無事反乱を鎮めることができたわけだが、これによって甲斐での源氏の権威は高まったのである。
その後、頼義、義家は陸奥の安部頼時、貞任の反乱(前九年の役)や、清原一族の反乱(後三年の役)を鎮定し、東国での源氏の声望は高まった。義光はこの後三年の役のときに兄義家の苦戦の情報を聞き、参戦して戦功をたてている。その後常陸介、甲斐守を歴任している。
さきに、新羅三郎義光が武田信玄の祖であると書いたが、べつに武田を名乗っていたわけではない。では武田の姓を初めて名乗ったのは誰なのであろうか?
茨城県ひたちなか市に武田地区というところがあるが、ここが「武田」発祥の地であるという説がある。
義光が常陸にいたころ、義業(よしなり)を佐竹郷に配し、義清を武田郷に配したというのである。この義清が初めて武田の姓を名乗ったというのだ。その後、義清はある事件に巻き込まれ、嫡男である清光とともに甲斐に流されて市河荘に移り、荘司として初めて甲斐に土着した。今でも市川大門町には義清館址や墳墓といわれているものがある。
義清の嫡男の清光は逸見冠者または黒源太とかいわれている。八ヶ岳山麓の逸見荘にいたためである。墓は長坂町の清光寺にある。
この清光には大勢の子があり、諸氏の祖となっている。このうち長男光長は父祖伝来の逸見荘を継ぎ、次男信義が武川荘武田に拠り武田を名乗った。この信義こそが武田氏の祖であり初めて武田を名乗ったという説もある。光長と信義は双生児であり従って二人とも太郎と称したという。しかし異母兄弟である説もある。清光は長男である光長に逸見を継がせている事実から、やはり武田の祖は信義のような気がする。
だれか知っている人がいたら教えてください。
どちらにせよ、武田氏は甲斐源氏の惣領として、「御旗」、「楯無」を代々受け継ぐことになる。これは新羅三郎義光が父頼義から受け継いだものであり、「御旗」は日本最古の日の丸とされている。ちなみに「楯無」は鎧である。
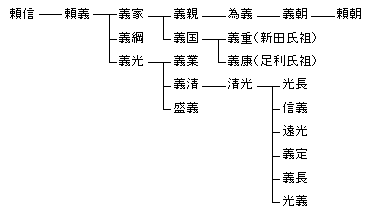
<源平合戦と甲斐源氏>
保元・平治の乱のころの甲斐源氏は清光とその息子たちの時代である。光長、信義は既に出てきたが、三男は遠光は加賀美姓を継ぎ、四男義定は安田姓を名乗る。この義定は実は義清の子であるらしい。それぞれが、武田、逸見、加賀美、安田、平井、河内、田井、八代、浅利、曽根等の祖となっている。
この両乱には、源義朝からの参戦の要請が甲斐源氏にあったにもかかわらず、清光は一族の本体を参加させること無く動かなかった。このため、この両乱を経た後の平家全盛時代に、甲斐源氏はほとんど打撃を受けることなくすんでいる。
しかしその後頼朝が挙兵するに及んで、武田信義を総帥とした甲斐源氏軍団は頼朝に協力し、というかむしろ頼朝と対等な立場で平家追討に活躍した。
1180年8月頼朝は伊豆で挙兵した後、石橋山で大庭景親に大敗し、箱根山中から房総半島へ逃れた。この状況下で北条時政らは甲斐源氏に救援を要請した。これにこたえて武田信義とその息子である忠頼らは、信濃の平氏側の武将を討ち、その後駿河に出兵する。ちょうどそのころ頼朝も関東の諸氏を率いて駿河に向っていた。甲斐源氏軍団は、信義、及び息子の忠頼、兼信、有義、信光、また信義の兄の逸見光長、弟である安田義定、河内義長(または長義)らが駿河の平氏方勢力を破り、頼朝とともに横瀬川(沼津市)でおちあった。その後富士川を挟んで、平氏方の平惟盛、忠度らと対峙することになる。ここで武田信義は夜敵陣の背後を襲おうとしたときに水鳥の大群が飛び立ち、これに驚いた平家軍は驚きのあまり戦うことなく退却したことは有名である。
これらの戦功により、信義は駿河守、安田義定は遠江守に任ぜられた。その後は義経らの活躍により平氏は壇ノ浦で滅亡する。もちろん甲斐源氏の諸将も各地にて奮闘する。
戦後、頼朝による一族の粛清の嵐に甲斐源氏も巻き込まれることになる。まず信義の嫡男忠頼が反乱の容疑で殺され、その後兼信、有義も成敗され、失意の中で信義も病没する。後の奥羽征伐後は安田義定、義資親子も謀殺される。結局生き残ったのは、加賀美遠光とその次男である小笠原長清、そして武田家直系では、信義の五男である信光であった。この小笠原長清の子孫が後に塩尻峠で信玄と戦うことになる小笠原長時である。
信光は今の石和町に本拠地を置き井沢五郎信光といったが、その後信玄の父信虎が本拠地をいまの甲府に移すまでの間この石和が武田氏の本拠地となる。承久の乱では信光は東山道大将軍となって小笠原長清らとともに遠征し幕府方の勝利におわり、信光は安芸守、長清は阿波守に任ぜられる。その後長清の子孫は阿波に土着するが、後年の三好氏の祖はこの小笠原長清であるという。その後武田氏は、信政、信時、時綱、信宗と続くが、詳しいことは良く分かっていない。
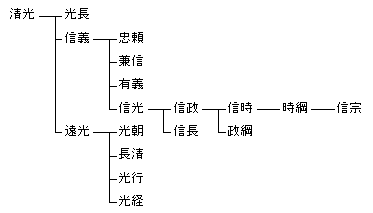
<南北朝時代>
新田義貞によって鎌倉の北条氏が滅ぼされ、その後足利尊氏の北朝方と後醍醐天皇の南朝方とによる南北朝の動乱期になるわけだが、このころの武田家は信宗の嫡男である信武である。信武は安芸守であったが、尊氏の挙兵とともに兵を起こし信武、信成親子は終始尊氏と行動をともにする。
北朝方は軍事的に優位な立場にありながら、高師直、尊氏と弟直義の対立によりなかなか全国の統一がなされず、時には直義が南朝方に寝返ったり尊氏、義詮親子が南朝方に降伏したりする有様である。
高師直の死後、尊氏は弟直義を討伐するために京都から関東へ攻めこむが、このとき武田信成らが直義と戦っている。尊氏と直義の和睦成立直後に直義が急死するが、その子直冬や後醍醐天皇の子である宗良親王、新田義宗等の勢力はまだまだあなどりがたく尊氏の苦労は続く。
宗良親王は越後や信濃を点々とするが信濃を拠点としていたときに征東大将軍に任ぜられ、新田氏らとともに鎌倉を占拠して尊氏を敗走させ、時を同じくして南朝方は京都も占拠し義詮も京都から逃れたが、その後尊氏らは鎌倉を奪還し南朝方の勢力は衰退した。しかし甲斐ではその後も武田氏による統一ができたとはいえず、信成の子信春は甲斐国内の南朝方勢力としばしば戦っている。
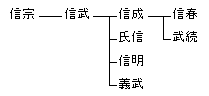
<武田家衰退の時代>
武田信春の嫡男である信満は自分の娘を、当時関東管領を名乗っていた上杉氏憲に嫁がせ上杉氏とは姻戚関係を結び親しい間柄であった。上杉氏は後に戦国時代には扇谷、山内の両上杉氏が有名であるが、氏憲は犬懸上杉氏であった。
関東管領とは尊氏が京都に幕府を開いた後、関東の武家勢力を押さえるために弟直義、その後長男義詮、その弟基氏を鎌倉に置きそれ以降は基氏の子孫が代々世襲していた。当時は関東8国、伊豆、甲斐、陸奥、出羽の12国を管轄し次第に京都の幕府に対抗する姿勢を見せはじめ、このころは関東公方と称し、執事である上杉氏が関東管領を名乗っていたのである。前執事の上杉氏憲(禅秀)が当時関東公方を名乗っていた足利持氏に反旗をひるがえして大乱を引き起こし勢いに乗って鎌倉を占拠するに至る。この上杉禅秀の乱に武田信満は氏憲方に味方し戦功をたてた。
しかし京都の幕府は足利持氏を支援することになり、関東の諸将に対して持氏支援を命じた。この結果上杉氏憲は鎌倉で自殺し、武田信満も戦いに敗れて甲斐へ帰国する途中に栖雲寺にて自殺する。これによって甲斐での武田氏は苦難の時代となる。もともと清光やその長男光長(武田信義の兄)は逸見姓を名乗っており甲斐源氏の宗家であったが武田信義以降武田氏にその地位を奪われていたのだが、この信満の死によって逸見有信は鎌倉の関東公方とむすび代々武田氏が世襲してきた甲斐の守護になれるよう足利持氏に嘆願したが守護の任命権は幕府が握っており幕府はそれを認めなかった。しかし甲斐は事実上逸見氏によって支配されてしまい、信満の子信重と、その叔父である信元とともに甲斐から脱出して高野山に逃れた。
幕府は信満の弟である信元を甲斐の守護に任命して信濃の小笠原氏に支援させて甲斐へ赴任させようとしたが信元が甲斐に戻れたかどうかはわからない。信元の死後信重が甲斐の守護に任命され、鎌倉側も信重を甲斐へ戻すかわりに武田の一族を鎌倉に出仕させるという条件を出したが、当時甲斐は逸見氏や穴山氏によって支配されており武田信重は甲斐には戻らなかった。甲斐では、信元の養子となっていた信長の子伊豆千代丸がいたが逸見氏の力は依然強く何ともできずにいた。
信重の弟信長(伊豆千代丸の実の父)は武田氏再興のため逸見氏や、守護代跡部氏らとしばしば戦いこれを苦しめたため足利持氏が親征することになり、さすがの信長も敗れ鎌倉に出仕していた。その後も信長は甲斐に攻めこむがこれもうまくいかず駿河から京都へ逃れた。
その後甲斐の情勢も変わり、守護代跡部氏が武田信重に服従し帰国してくれるように嘆願するが、幕府が許さなかったためすぐには帰国できなかったが、それから4年後鎌倉方と幕府との戦いが起き、その渦中にまぎれて信重の21年ぶりの帰国が実現した。帰国後すぐに宿敵逸見氏を滅ぼし甲斐の守護としての地位を確保した。
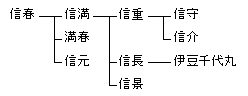
<武田信昌、信縄>
武田信重は甲斐に帰国して12年後に没し、弟である武田信長は上総に土着してしまうことになる。信重の死の5年後に子の信守も没してしまう。その後を継いだのがまだ9歳であった武田信昌である。逸見氏は滅んだが、守護代の跡部氏(駿河、上野父子)の力が強く武田と跡部の血みどろの戦いが続く。守護代跡部父子の専横ぶりに対して武田一族は結束して戦うが一時は大敗して危機に陥ってしまう。しかし信昌18歳のときに跡部駿河が没した機会に諏訪と協力して跡部を討ち、ついに跡部氏を滅ぼすことに成功する。
このころ関東では古河公方(足利)と関東管領(上杉)の対立が続いており、ときの将軍足利義政は、甲斐の武田信昌と駿河の今川義忠に対して古河公方足利成氏追討令を出すが、跡部との抗争中でもあり出陣することはできなかった。
その後信濃の諸豪族が何度も甲斐に進入しそれに呼応して甲斐国内の勢力の反乱が繰り返され、更に飢饉や疫病の流行などもあり甲斐国は悲惨な状況となるが信昌は次男の信恵に家督を譲ろうとして長男信縄と対立し内戦状態となってしまう。信昌・信恵と信縄の抗争に乗じて今川氏親や伊勢長氏らが甲斐への侵略が繰り返される。
しかし1505年に信昌が死ぬと2年後には信縄も死去し、長男の信虎が14歳で家督を継いだ。
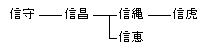
|