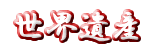

2005年に登録、2007年に登録内容が変更された世界遺産(自然遺産)で、メキシコ北西部、
メキシコ本土とバハ・カリフォルニア半島との間の南北に細長いカリフォルニア湾にある。
湾内のアンヘル・デ・ラ・グアルダ島やティブロン島など244の島々や海岸など9ヵ所の保護地域を含む。
この地域では海洋地形が形成される全過程が観察できる。また、半閉鎖性の湾内は海洋生物の宝庫となっている。
湾内の島々は、アメリカオオアジサシ、オグロカモメなどの海鳥の繁殖場となっているほか、
クジラ、イルカ、カリフォルニアアシカ、シャチ、ゾウアザラシなど海生哺乳動物が回遊している。
また、北部には、絶滅危惧種のコガシラネズミイルカなど多くの固有種が生息している。
生態系と生物多様性の保全を目的に、世界遺産に登録された。

1987年に登録されたメキシコの世界遺産(文化遺産)で、メキシコ・シティの中央広場(ソカロ)を中心にスペイン植民地時代の
建築物が立ち並ぶ地域と、メキシコ・シティの南約20kmにある水郷ソチミルコを指す。16世紀初め、アステカ帝国を滅ぼした
スペイン人は、直ちに植民地の首都の建設を始めた。240m四方の中央広場には、250年もの歳月をかけて改築された
大聖堂をはじめ、国立宮殿、アラメダ公園などの遺産が残っている。1978年、電気工事中に大聖堂裏で
一枚岩の円盤が発見され、その後の発掘で大神殿が姿を現した。ここは、かつてアステカ帝国の都として栄えた場所で、
しかも湖上に浮かんでいた。
スペイン人は、湖を埋め立て、アステカの建造物を破壊した上に建物を建てた。一方、ソチミルコでは、
アステカ人が生み出したチナンパ(浮き畑)と呼ばれる独創的な農耕法が受け継がれている。
このような文化的価値が評価され、メキシコ・シティ歴史地区と共に世界遺産に登録された

1987年に登録された世界遺産(文化遺産)で、メキシコ中央部、マリンチェ火山の麓に位置する。プエブラは、
プエブラ州の州都で、正式名称は、プエブラ・デ・サラゴサ(Puebla de Zaragoza)。
1531年にキリスト教のフランシスコ会の宣教団が町を建設した。豊かな高原地帯に位置することから、
農業経済の中心、またメキシコ・シティとメキシコ湾岸のベラクルスを結ぶ交通の要衝として発展した。
中央広場に建つ大聖堂は、1649年に完成し、内部は縞メノウや大理石、金の縁飾りなどで装飾されている。
サント・ドミンゴ聖堂の中に、黄金の内部装飾で知られるロサリオ礼拝堂がある。
町には、外観が赤茶色の装飾タイルと白漆喰の「砂糖菓子の家」など、色彩豊かな装飾が施されている建物が数多く残っている。
ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院 1994年 文化遺産 (撮影:2016年 8月21日) お勧め度:6

1994年に登録されたメキシコの世界遺産(文化遺産)で、メキシコ・シティ南東約60km、標高5452mのポポカテペトル山の
山麓一帯にある。1521年、コルテスがこの地を征服すると、スペインからドミニコ修道会、フランシスコ修道会、
アウグスティヌス修道会などキリスト教各会派の修道士がメキシコを訪れた。そして彼らは、1525年から、
ポポカテペトル山の西斜面に位置するクエルナバカに修道院を建設し、先住民への布教活動を始めた。
これを皮切りに、山麓一帯に次々と修道院が建てられ、16世紀末には300以上にのぼった。この地の修道院の特徴は、
礼拝堂が屋外に設けられていることである。これは、土着の宗教儀式が屋外で行われていたことから、
先住民に受け入れられやすいようにしたものである。このような屋外開放型礼拝堂という特異な構造を
有する16世紀の修道院のうち、ポポカテペトル山麓にある14の修道院がその代表的な建造物として評価され、
世界遺産に登録された。万m2ほどの面積である。宮殿の正門は、アヤソフィアの側にある「帝王の門」(バーブ・ヒュマーユーン)である。

シウダ・ウニベルシタリアは開かれた場所であることが企図されている。かつては火山岩盤あり、鬱蒼と茂った
植生ありといった状況だったので、まっすぐ伸びた道などはほとんどない。道路は同心円状にめぐらされ、
そこに各建物が配置されている。建物には徒歩5 - 10分程度の間隔で配置されているものもある。
かつて転がっていた火山岩はどかされ、建物の部屋、小道、壁面などの建材に転用された。
建物それ自体は、コンクリートと煉瓦を主体とする共通の建材が用いられている。建物の多くは数階建てで、
窓が大きくとられ、内外に庭園が配置されている。

1987年に登録されたメキシコの世界遺産(文化遺産)で、メキシコ・シティ北東約50kmの標高2000mを超える高地にある。
テオティワカンはメキシコ最初の文明の発祥地で、紀元前2世紀頃に誕生し、紀元7世紀半ばまでメキシコ高原地帯で栄えた。
その影響は、メソアメリカの他文明(マヤ文明など)、後のアステカ文明にまで及んだ。テオティワカンは
「神々の集う場所」という意味で、廃墟となったこの地を発見したアステカ人が、神殿の壮大さに驚嘆し、
神々が集まり太陽と月を創造した聖地と考え、こう名付けたという。都の中央を、幅40m、長さ約5kmの「死者の大通り」が
南北に貫き、その周辺に「太陽のピラミッド」や「月のピラミッド」など600基近いピラミッドや宮殿、住居などが
整然と建ち並んでいる。太陽のピラミッドの高さは63m、月のピラミッドの高さは46mで、
これらの神殿の壁面は、赤と白の漆喰で塗られ、多彩色の壁画が描かれた。

1996年に登録された世界遺産(文化遺産)で、メキシコのユカタン半島北部のプウク地方にある。ウシュマルは、
6世紀頃に熱帯雨林に覆われた丘陵地帯に築かれ、7〜10世紀頃に繁栄したマヤ文明を代表する都市遺跡の一つで、
最盛期の人口は約2万5000人に達したという。遺跡は、東西約600m、南北約1kmで、南北にプウク様式の建造物が建ち並ぶ。
プウク様式は、通常のマヤ建築と異なり、建物が横長の方形で、平らな屋根を持ち、壁にはコンクリートが用いられる一方、
壁面の上半分には切り石のモザイク装飾が施されている。遺跡群の南側にある「総督の館」は、約2万個の切り石で
装飾されたプウク様式の最高傑作とされる。その北側にある「魔法使いのピラミッド」は、他のマヤ文明の都市には
見られない楕円形のピラミッドである。その他に尼僧院、球戯場など全部で15の建造物が残っている。
このような古代遺跡の魅力が評価され、世界遺産に登録された。

88年に登録された世界遺産(文化遺産)で、メキシコのユカタン半島北部の密林の中にある。古代マヤ文明の
都市チチェン-イッツァは、5世紀の半ばに築かれた。7世紀末に一度滅びたものの、11世紀にマヤとトルテカの二大文明が
融合する都市として復興し、13世紀頃まで栄えた。そのため遺跡は、トルテカ文明の影響を受ける以前の
南側の地域を旧チチェン、それ以後の北側の地域を新チチェンと分けて呼ばれている。チチェン-イッツァは、マヤ語で
「泉のほとりの水の魔術師」を意味し、「セノーテ」と呼ばれる天然の泉を中心に発展した。旧チチェンには、
円筒形の建物「カラコル」(スペイン語で「カタツムリ」の意)と女子修道院が残っている。カラコルは天体観測所であり、
女子修道院は宮殿として使われていたとされる。新チチェンには、頂上部にククルカンの神殿がある
9層のピラミッド「エル・カスティーリョ」、球戯場、生け贄の心臓が供えられたというチャクモール像などがある。
エル・カスティーリョは「暦ピラミッド」とも呼ばれる。これらの建築物や像は、古代マヤ文明の特徴を示すものであり、
そうした重要な文化遺産であることが評価され、世界遺産に登録された。