キリスト教を知るために
このページのBGMは,ShibataさんのMIDIで聴く「マタイ受難曲」から
ソプラノ・アリア 「血を流せ,わが心よ!」です。
エーゲ海の修道士 聖山アトスに生きる
川又一英 著(集英社)¥1,600
 荒っぽい言い方をすれば,キリスト教における修道院制は,自分自身の信仰生活を基盤とするという点で,自らの悟りを開くことを第一とする小乗仏教に通じるものがある。現在でも欧米には大小合わせて数多くの修道院があるが,観光地化していたり,事業を幅広く手がけるなど,すっかり世俗化している修道院も少なくない。その中にあって,修道院が本来の形で残っており,修道士たちが原始キリスト教的修道生活を頑なに守っているところが,本書に登場するギリシャのアトス半島にある「聖山アトス」なのである。ところが,女人禁制,電気も電話もないという現代と隔絶したアトスに入山を求める人は後をたたないという。ちょうど2003年のNHKスペシャルでアトスの特集が放映された(これはテレビカメラがアトスへ入ることを許された初めてのケースだったらしい)が,これもアトスへの関心が高まっていることへの現れだろう。
荒っぽい言い方をすれば,キリスト教における修道院制は,自分自身の信仰生活を基盤とするという点で,自らの悟りを開くことを第一とする小乗仏教に通じるものがある。現在でも欧米には大小合わせて数多くの修道院があるが,観光地化していたり,事業を幅広く手がけるなど,すっかり世俗化している修道院も少なくない。その中にあって,修道院が本来の形で残っており,修道士たちが原始キリスト教的修道生活を頑なに守っているところが,本書に登場するギリシャのアトス半島にある「聖山アトス」なのである。ところが,女人禁制,電気も電話もないという現代と隔絶したアトスに入山を求める人は後をたたないという。ちょうど2003年のNHKスペシャルでアトスの特集が放映された(これはテレビカメラがアトスへ入ることを許された初めてのケースだったらしい)が,これもアトスへの関心が高まっていることへの現れだろう。
美しいギリシャの半島の一画で修道士たちがどのような修道生活を送っているかということはそれだけでも興味のあることであるし,カトリックではなくギリシャ正教の修道院であるということで何かエキゾチックな興趣も湧いてくる。アトスの地形,歴史,修道院などの建物,修道士の日常の仕事や暮らしぶりはそれ自体興味深い。しかし,著者自身がアトスに惹かれた最も大きな理由は,なぜある人が家族や仕事を捨ててわざわざアトスに来たのか,アトスで神と共に生きることはその人にとってどういう意味を持つのか,といった人間の内面のドラマの中にあるように思う。そのドラマに限りない魅力を覚えたからこそ,著者は何度もアトスを訪れ,修道士たちと生活を共にしてきたのである。聖山アトスは厳しい修行の地であるが,同時に悩み求める人を受け容れる優しさを持っている。それはずっと昔からそうだったし,これから先もずっとそうであろう。こういう奇跡のような地が世界には残っている。本書を読めばそれが分かる。
こどものためのイエス・キリスト物語
ブライアン・ワイルドスミス 絵・文/星野真理 訳(小学館)¥1,600
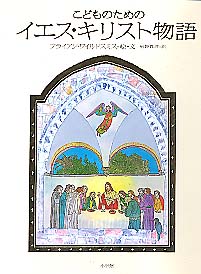 作者が英国人ということもあるが,ここで一冊の美しい絵本を。英国絵本界の大御所ブライアン・ワイルドスミスは1930年にヨークシャーに生まれ,バーンズレイ美術学校,ロンドン大学を卒業後,数学・音楽の教師を経て絵本画家として独立。彼の経歴からもうかがわれるように,ワイルドスミスの作風は非常によく計算された緻密なものであり,構図のバランスがよく,絵も実に細かいところまで気をつかって描きこんでいる。本書は聖書の福音書のイエス・キリスト伝をもとにした美しくカラフルな絵本である。しかし,原色を多用していても「どぎつい」という感じは全くしない。さらっとした線で描いているようで登場人物の表情が実に豊かである。いちばん大切なイエスの描き方は気品と威厳を感じさせるものだ。内容からいってクリスチャンの親が幼い子どもに読み聞かせするにもよかろうが,どなたにでもイースターやクリスマスの機会にぜひ一度見て読んでいただきたい傑作絵本である。
作者が英国人ということもあるが,ここで一冊の美しい絵本を。英国絵本界の大御所ブライアン・ワイルドスミスは1930年にヨークシャーに生まれ,バーンズレイ美術学校,ロンドン大学を卒業後,数学・音楽の教師を経て絵本画家として独立。彼の経歴からもうかがわれるように,ワイルドスミスの作風は非常によく計算された緻密なものであり,構図のバランスがよく,絵も実に細かいところまで気をつかって描きこんでいる。本書は聖書の福音書のイエス・キリスト伝をもとにした美しくカラフルな絵本である。しかし,原色を多用していても「どぎつい」という感じは全くしない。さらっとした線で描いているようで登場人物の表情が実に豊かである。いちばん大切なイエスの描き方は気品と威厳を感じさせるものだ。内容からいってクリスチャンの親が幼い子どもに読み聞かせするにもよかろうが,どなたにでもイースターやクリスマスの機会にぜひ一度見て読んでいただきたい傑作絵本である。
イエスとその時代
荒井 献 著(岩波新書)¥520
 キリスト教の始祖にして「神の子」であるイエスに「歴史的に接近」する。これが本書の著者がめざしたものである。簡単そうで実はこれは大変難しいことである。聖書の記述のどこまでが歴史的事実で,どこまでが伝承で,どこまでが後世の意図的加筆なのか。これらの問題点を含めて聖書を研究する「聖書学」という学問分野がある。一方で歴史学的なアプローチから初期キリスト教の実像を探ろうという研究も数多い。2000年あまり前という大昔のできことだが,研究者たちの努力により,イエスとその時代について,今なお新しい研究成果が報告され続けているのだ。歴史学者・聖書学者にとって,聖書は(最も重要な史料・文献であることには違いないが)「絶対」的な書物ではなく,むしろその他の多くの歴史的な史料と照らし合わせて成立の過程をひとつひとつ検証すべきものである。こうしたアプローチの結果,著者は伝承の最古層,つまり最も初期のキリスト教会においては,未だイエスの復活信仰は明確な形で現れていないという結論に至る。この点については,著者自ら「あとがき」の中で「復活信仰なしにはイエスを理解できないと信じている人々にとって,本書の内容は当然不満であろう。…しかし,信仰をドグマ化して,イエス理解の歴史的多様性を切り捨ててはなるまい。」と述べている。実際この本の読後感がよいのは,史料にもとづいた緻密な歴史的考証により,イエスとその時代の実際の姿を説得力をもって「再現」しているからだと思う。
キリスト教の始祖にして「神の子」であるイエスに「歴史的に接近」する。これが本書の著者がめざしたものである。簡単そうで実はこれは大変難しいことである。聖書の記述のどこまでが歴史的事実で,どこまでが伝承で,どこまでが後世の意図的加筆なのか。これらの問題点を含めて聖書を研究する「聖書学」という学問分野がある。一方で歴史学的なアプローチから初期キリスト教の実像を探ろうという研究も数多い。2000年あまり前という大昔のできことだが,研究者たちの努力により,イエスとその時代について,今なお新しい研究成果が報告され続けているのだ。歴史学者・聖書学者にとって,聖書は(最も重要な史料・文献であることには違いないが)「絶対」的な書物ではなく,むしろその他の多くの歴史的な史料と照らし合わせて成立の過程をひとつひとつ検証すべきものである。こうしたアプローチの結果,著者は伝承の最古層,つまり最も初期のキリスト教会においては,未だイエスの復活信仰は明確な形で現れていないという結論に至る。この点については,著者自ら「あとがき」の中で「復活信仰なしにはイエスを理解できないと信じている人々にとって,本書の内容は当然不満であろう。…しかし,信仰をドグマ化して,イエス理解の歴史的多様性を切り捨ててはなるまい。」と述べている。実際この本の読後感がよいのは,史料にもとづいた緻密な歴史的考証により,イエスとその時代の実際の姿を説得力をもって「再現」しているからだと思う。
キリスト教の本(上)
(学研)¥1,200
 この上下からなる「キリスト教の本」には,キリスト教やイエス・キリストについての批判的な記述もあるから,信者の方にはあまりお薦めできないが,キリスト教という宗教の歴史的・文化的・習俗的な側面に関心がある方には,「普通」のキリスト教本にはまずのっていないような内容がたくさん盛り込まれているから,一読をお薦めしたい(とくに下巻)。本の装丁は安物の観光ガイドブックみたいでちょっといただけないが…。
この上下からなる「キリスト教の本」には,キリスト教やイエス・キリストについての批判的な記述もあるから,信者の方にはあまりお薦めできないが,キリスト教という宗教の歴史的・文化的・習俗的な側面に関心がある方には,「普通」のキリスト教本にはまずのっていないような内容がたくさん盛り込まれているから,一読をお薦めしたい(とくに下巻)。本の装丁は安物の観光ガイドブックみたいでちょっといただけないが…。
この上巻「救世主イエスと聖書の謎を解く」には「イエス・キリスト伝」を中心に,「古代キリスト教史」や「キリスト教論争史」,「週末と千年王国」といったトピックスが取り上げられている。豊富な写真で解説された「聖遺物の謎」が興味深い。
キリスト教の本(下)
(学研)¥1,200
 上巻に続く下巻は「聖母・天使・聖人と全宗派の儀礼」編である。全編興味深いが,とくに三大宗派(カトリック,正教,プロテスタント)の儀礼を写真や図版を多く使って,これだけ詳細かつ具体的に解説した本は他にはなかなかなく,史料としても貴重である。「十字架と文字のシンボリズム」も民俗学として大変おもしろい。普通の日本人がイメージする十字架は短い横木と長い縦木を組み合わせたシンプルな「ラテン十字」だが,世界には様々な形をした十字架がたくさんある。英国のウェールズやコーンウォールにある「ケルト十字」がのっていないのがちょっと残念。巻末特集として,カトリック,東方正教会系,英国国教会,プロテスタント系,諸教と新宗教に分けてキリスト教全宗派の総覧があり,これも欧米社会の宗教的・文化的バックグラウンドを知る上で貴重な史料である。
上巻に続く下巻は「聖母・天使・聖人と全宗派の儀礼」編である。全編興味深いが,とくに三大宗派(カトリック,正教,プロテスタント)の儀礼を写真や図版を多く使って,これだけ詳細かつ具体的に解説した本は他にはなかなかなく,史料としても貴重である。「十字架と文字のシンボリズム」も民俗学として大変おもしろい。普通の日本人がイメージする十字架は短い横木と長い縦木を組み合わせたシンプルな「ラテン十字」だが,世界には様々な形をした十字架がたくさんある。英国のウェールズやコーンウォールにある「ケルト十字」がのっていないのがちょっと残念。巻末特集として,カトリック,東方正教会系,英国国教会,プロテスタント系,諸教と新宗教に分けてキリスト教全宗派の総覧があり,これも欧米社会の宗教的・文化的バックグラウンドを知る上で貴重な史料である。
同情の心 −シリアの聖イサクによる黙想の60日−
A・M・オーチン 編/S・ブロック 英訳/梶原史郎 訳(聖公会出版)¥1,456
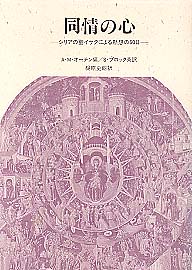 シリアの聖イサクとは,7世紀にシリアの正教会で活躍した聖人である。ニネベの聖イサクの名前でも知られている。聖イサクの時代,キリスト教徒とイスラム教徒は必ずしも敵対関係にはなく,祈りの修行をする人たちの間には,しばしば宗教の違いを越えて親密な交流や友好関係があったという。現在では西洋の衣をまとった宗教というイメージがすっかり定着しているキリスト教だが,聖イサクの時代の東方正教会は,国,民族,言語,政治体制などの違いを乗り越えて,キリストの真の福音を述べ伝えるための情熱にあふれていたのだろう。そういう聖イサクの言葉には,一貫して口先だけではない他者に対する真の同情と寛容の精神が流れている。それが本書のタイトルにもなっているわけである。西洋のキリスト教徒が,その後の歴史において十字軍遠征や,旧教徒と新教徒間の熾烈な宗教戦争のような愚行を繰り返したことを考えるとき,また現在も世界中で存在する宗教的対立を考えるとき,聖イサクの言葉は21世紀の私たちにも実感をもって響いてくるだろう。聖イサクの考え方が明確に現れた一節をあげたい。「神へのあなたの負債が極めて大きいにもかかわらず,神はあなたに支払いを促すような気配を全くお見せにならない。かえって,あなたが現すどんな小さな善意の行いにも豊かに報いて下さる。神を「正義」のお方として語ってはならない。神の正義は,あなたに対する神の行いの中には見い出すことができないからである。」
シリアの聖イサクとは,7世紀にシリアの正教会で活躍した聖人である。ニネベの聖イサクの名前でも知られている。聖イサクの時代,キリスト教徒とイスラム教徒は必ずしも敵対関係にはなく,祈りの修行をする人たちの間には,しばしば宗教の違いを越えて親密な交流や友好関係があったという。現在では西洋の衣をまとった宗教というイメージがすっかり定着しているキリスト教だが,聖イサクの時代の東方正教会は,国,民族,言語,政治体制などの違いを乗り越えて,キリストの真の福音を述べ伝えるための情熱にあふれていたのだろう。そういう聖イサクの言葉には,一貫して口先だけではない他者に対する真の同情と寛容の精神が流れている。それが本書のタイトルにもなっているわけである。西洋のキリスト教徒が,その後の歴史において十字軍遠征や,旧教徒と新教徒間の熾烈な宗教戦争のような愚行を繰り返したことを考えるとき,また現在も世界中で存在する宗教的対立を考えるとき,聖イサクの言葉は21世紀の私たちにも実感をもって響いてくるだろう。聖イサクの考え方が明確に現れた一節をあげたい。「神へのあなたの負債が極めて大きいにもかかわらず,神はあなたに支払いを促すような気配を全くお見せにならない。かえって,あなたが現すどんな小さな善意の行いにも豊かに報いて下さる。神を「正義」のお方として語ってはならない。神の正義は,あなたに対する神の行いの中には見い出すことができないからである。」
聖山アトスの修道者 シルワンの手記
古谷 功 監修/エドワード・ブジョストフスキ 訳(あかし書房)¥900
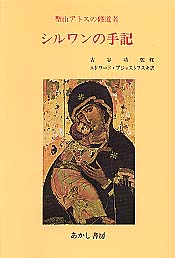 シルワンと聞いて誰かのように「汁あん(おしるこ)」を想像してはいけない。シルワンは1866年中央ロシアに生まれた貧しい農民だったが,26歳のときに聖山とされるアトス山に入り,1938年に没するまでずっと修道者としての生活を送った人物である。聖山アトスでの修道は,霊的な体験を重んじる正教の伝統であり,その修道生活自体が必ずしも特別なことであるとはいえない。しかし,アトスでの深い霊的体験を簡潔で美しい手記に残したことによって,彼の名前は不滅のものとなった。在世中から名声が高かったにもかかわらず,高い地位などには目もくれず,最後まで一介の修道士で通したシルワンが求めたものは徹底した「謙虚さ」であった。真に謙虚な人だけが言うことのできる謙虚な言葉がクリスチャンでない者の心をも打つ。
シルワンと聞いて誰かのように「汁あん(おしるこ)」を想像してはいけない。シルワンは1866年中央ロシアに生まれた貧しい農民だったが,26歳のときに聖山とされるアトス山に入り,1938年に没するまでずっと修道者としての生活を送った人物である。聖山アトスでの修道は,霊的な体験を重んじる正教の伝統であり,その修道生活自体が必ずしも特別なことであるとはいえない。しかし,アトスでの深い霊的体験を簡潔で美しい手記に残したことによって,彼の名前は不滅のものとなった。在世中から名声が高かったにもかかわらず,高い地位などには目もくれず,最後まで一介の修道士で通したシルワンが求めたものは徹底した「謙虚さ」であった。真に謙虚な人だけが言うことのできる謙虚な言葉がクリスチャンでない者の心をも打つ。
キリスト教入門
矢内原忠雄 著(角川選書)¥980
 「無教会主義」を唱えた明治の偉人内村鑑三の弟子であり,第二次大戦後の日本が貧しい時期に東大総長を務めた矢内原忠雄が著した今や古典ともいってよい著作である。著者は日本を民主化させるためには日本人がキリスト教を理解することが不可欠であるとの信念にもとづき,キリスト教を知らない若き学生にキリスト教の知識を伝えようとした。現在の目でこの本の内容自体をどうのこうの言うよりも,当時の社会情勢の中で著者が何を考え,何を伝えたかったということが明確に伝わってくるという点が重要だと思う。彼の考えを受け入れるにせよ,受け入れないにせよ,当時の学生はまじめにこの本と向きあったことだろう。戦後すぐの時代よりはずっと豊かだが,一方で夢と希望を失いつつある今の閉塞した日本を見て著者はどのように感じるだろうか。
「無教会主義」を唱えた明治の偉人内村鑑三の弟子であり,第二次大戦後の日本が貧しい時期に東大総長を務めた矢内原忠雄が著した今や古典ともいってよい著作である。著者は日本を民主化させるためには日本人がキリスト教を理解することが不可欠であるとの信念にもとづき,キリスト教を知らない若き学生にキリスト教の知識を伝えようとした。現在の目でこの本の内容自体をどうのこうの言うよりも,当時の社会情勢の中で著者が何を考え,何を伝えたかったということが明確に伝わってくるという点が重要だと思う。彼の考えを受け入れるにせよ,受け入れないにせよ,当時の学生はまじめにこの本と向きあったことだろう。戦後すぐの時代よりはずっと豊かだが,一方で夢と希望を失いつつある今の閉塞した日本を見て著者はどのように感じるだろうか。
ガリラヤからローマへ
松本宣郎 著(山川出版社)¥2,700
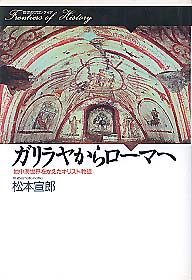 この本には「地中海世界をかえたキリスト教徒」という副題がついている。世界史,とくに西洋史が好きな者にとって,偉大な古代ローマ帝国の時代ほどスリリングでおもしろい時代は少ないだろう。イタリア在住の作家,塩野七生氏が取り組んでいる「ローマ人」のシリーズがベストセラーになっているのも,一つにはこの時代そのものが波乱万丈のスリリングなドラマであるということがあるだろう。日本史でいえば多くの部将が覇を競った戦国時代にあたるだろうか。著者が本書で意図したのは,あとがきに書かれているように,初期のキリスト教徒とローマ社会,ローマ人との関係を歴史的に明らかにするということである。昔習った高校の世界史の教科書だと,「古代ローマでは,キリスト教徒の勢力がだんだん増して,ついにコンスタンティヌス大帝がキリスト教をローマの国教にした。」という程度の記述しかなかったと思うが,この本ではそれに至るまでのキリスト教徒への迫害,非キリスト教徒との相克の歴史が多くの歴史資料をもとにして克明に描かれている。当時の人たちがどのような価値観を持って生きていたかということがいきいきと伝わってくる本である。
この本には「地中海世界をかえたキリスト教徒」という副題がついている。世界史,とくに西洋史が好きな者にとって,偉大な古代ローマ帝国の時代ほどスリリングでおもしろい時代は少ないだろう。イタリア在住の作家,塩野七生氏が取り組んでいる「ローマ人」のシリーズがベストセラーになっているのも,一つにはこの時代そのものが波乱万丈のスリリングなドラマであるということがあるだろう。日本史でいえば多くの部将が覇を競った戦国時代にあたるだろうか。著者が本書で意図したのは,あとがきに書かれているように,初期のキリスト教徒とローマ社会,ローマ人との関係を歴史的に明らかにするということである。昔習った高校の世界史の教科書だと,「古代ローマでは,キリスト教徒の勢力がだんだん増して,ついにコンスタンティヌス大帝がキリスト教をローマの国教にした。」という程度の記述しかなかったと思うが,この本ではそれに至るまでのキリスト教徒への迫害,非キリスト教徒との相克の歴史が多くの歴史資料をもとにして克明に描かれている。当時の人たちがどのような価値観を持って生きていたかということがいきいきと伝わってくる本である。
修道院
朝倉文市 著(講談社現代新書)¥650
 ヨーロッパの教会や修道院に行くと,そこが属している修道会派として,ベネディクト派,ドミニコ会,フランシスコ(フランチェスコ)会などの名称が書かれていることがよくある。それらの修道会がいつ頃どのような経緯でできたのか,創設者はどのような人物だったのかということには以前から興味を持ちつつも,手軽な本が身近にはなかった。それだけにこの本が出たときは嬉しかった。修道制の起源に始まり,代表的な修道会の紹介,修道士の日常生活,修道会の歴史的変遷などがわかりやすくコンパクトに述べられている。著者は,「修道院生活」は,古来隠遁と清貧の思想になじみ親しんできた日本人の心性とも共通したものがあるとエピローグで述べている。禅宗の僧の修行とも相通ずるものがあるように思うがどうだろう。修道士や修道女のことを世の中から逃避しているだけの人と思っている人も多いだろうが,今は修道院も社会に役立つことをし,商売や観光にも力を入れなければ絶対に生き残れない時代だろう。アッシジの聖フランチェスコ教会で,ジョットの「小鳥に説教する聖フランチェスコ」の画を立て板に水という感じで説明してくれた日本人修道士のことを思い出す。修道院でさえ「禁欲と観想」の生活を送ることはもはや難しいのかもしれない。
ヨーロッパの教会や修道院に行くと,そこが属している修道会派として,ベネディクト派,ドミニコ会,フランシスコ(フランチェスコ)会などの名称が書かれていることがよくある。それらの修道会がいつ頃どのような経緯でできたのか,創設者はどのような人物だったのかということには以前から興味を持ちつつも,手軽な本が身近にはなかった。それだけにこの本が出たときは嬉しかった。修道制の起源に始まり,代表的な修道会の紹介,修道士の日常生活,修道会の歴史的変遷などがわかりやすくコンパクトに述べられている。著者は,「修道院生活」は,古来隠遁と清貧の思想になじみ親しんできた日本人の心性とも共通したものがあるとエピローグで述べている。禅宗の僧の修行とも相通ずるものがあるように思うがどうだろう。修道士や修道女のことを世の中から逃避しているだけの人と思っている人も多いだろうが,今は修道院も社会に役立つことをし,商売や観光にも力を入れなければ絶対に生き残れない時代だろう。アッシジの聖フランチェスコ教会で,ジョットの「小鳥に説教する聖フランチェスコ」の画を立て板に水という感じで説明してくれた日本人修道士のことを思い出す。修道院でさえ「禁欲と観想」の生活を送ることはもはや難しいのかもしれない。
パリのマリア
竹下節子 著(筑摩書房)¥2,800
 本書には「ヨーロッパは奇跡を愛する」という副題がついている。長年カトリック国のフランスに住んでいる著者は,神秘主義と超常現象が結びついたキリスト教の「奇跡」を,一見合理的なこの国の中に発見する。その「奇跡」を起こした3人の聖女の物語が,「パリのマリア」,「闇の中のロゴス」,「天翔る聖女」として一冊にまとめられたのがこの本だ。「遺体が腐らない」とか「聖痕から血を流す」とかいう「奇跡」は,興味本位のテレビ番組でもネタになることがあるが,この本の内容はそのようなレベルで終わっているのではない。どういう背景で一人の娘が奇跡を起こす聖女となったのか,奇跡を教会や民衆はどのように受け止めたか,ヨーロッパの歴史において奇跡はどのように扱われてきたか,といったことが話題の中心となる。中沢新一氏が「はじめてのフランスに出会える」と絶賛したユニークな好著である。
本書には「ヨーロッパは奇跡を愛する」という副題がついている。長年カトリック国のフランスに住んでいる著者は,神秘主義と超常現象が結びついたキリスト教の「奇跡」を,一見合理的なこの国の中に発見する。その「奇跡」を起こした3人の聖女の物語が,「パリのマリア」,「闇の中のロゴス」,「天翔る聖女」として一冊にまとめられたのがこの本だ。「遺体が腐らない」とか「聖痕から血を流す」とかいう「奇跡」は,興味本位のテレビ番組でもネタになることがあるが,この本の内容はそのようなレベルで終わっているのではない。どういう背景で一人の娘が奇跡を起こす聖女となったのか,奇跡を教会や民衆はどのように受け止めたか,ヨーロッパの歴史において奇跡はどのように扱われてきたか,といったことが話題の中心となる。中沢新一氏が「はじめてのフランスに出会える」と絶賛したユニークな好著である。
ギリシャ正教
高橋保行 著(講談社学術文庫)¥900
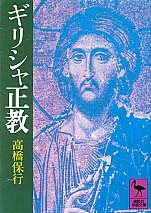 キリスト教といえば西洋のものというイメージが強い。さらに,日本のキリスト教会では,カトリックとプロテスタントの勢力が圧倒的に強い。函館のハリストス正教会のように,一般に名の知れた正教会もあることにはあるが,絶対数が少ない。このような状況では,正教会について知ることのできる機会は残念ながら多いとはいえないだろう。本書はギリシャ正教の全貌を日本ではじめて明らかにした画期的著作。これ一冊でギリシャ正教の歴史,思想,儀礼が分かる。
キリスト教といえば西洋のものというイメージが強い。さらに,日本のキリスト教会では,カトリックとプロテスタントの勢力が圧倒的に強い。函館のハリストス正教会のように,一般に名の知れた正教会もあることにはあるが,絶対数が少ない。このような状況では,正教会について知ることのできる機会は残念ながら多いとはいえないだろう。本書はギリシャ正教の全貌を日本ではじめて明らかにした画期的著作。これ一冊でギリシャ正教の歴史,思想,儀礼が分かる。
例えば,西洋のキリスト教(カトリック,プロテスタント)では,原罪を持つ堕落した人間を救済するためにイエス・キリストが生まれたと考えるが,東洋のキリスト教である正教会では,このような二元論的(聖・俗)な考え方は希薄で,人間は神によって善なるものとして創造されたということを強調する。言うなれば性善説である。人間が堕落しているのは,神が創造したときの善なるイメージを失ってしまっているからだとする。その神が善しとするイメージを回復するためにキリストの救いが必要なのだと考える。このように,キリスト教と一口にいっても,正教の考え方は西洋のキリスト教とはかなり違うということを改めて認識させられる。
ロシア精神の源
高橋保行 著(中公新書)¥540
 上の「ギリシャ正教」と同じ著者が今度はロシアのこころの源流を語る。「よみがえる「聖なるロシア」」という副題からも想像がつくように,著者はロシア精神の源は正教の伝統だとし,ロシアとビザンチン帝国や他のヨーロッパ諸国との歴史的関わりの中からロシアという国をとらえ直そうとしている。実は本書はソ連邦が崩壊する前に刊行された本なのだが,著者の予見した「聖なるロシア」の復活は現在いっそう進んでいるかもしれない。ロシアは政治,経済,軍事の面からばかり見られることが多いという著者が指摘している状況は,残念ながらソ連邦が崩壊した現在でも変わっていない。もっとロシアの豊かな精神文化に目を向けようではないかという著者の主張には共感するものが多い。ロシアで昔から大切に守られてきた聖なるイコンをいつの日かこの目で見てみたいと思う。
上の「ギリシャ正教」と同じ著者が今度はロシアのこころの源流を語る。「よみがえる「聖なるロシア」」という副題からも想像がつくように,著者はロシア精神の源は正教の伝統だとし,ロシアとビザンチン帝国や他のヨーロッパ諸国との歴史的関わりの中からロシアという国をとらえ直そうとしている。実は本書はソ連邦が崩壊する前に刊行された本なのだが,著者の予見した「聖なるロシア」の復活は現在いっそう進んでいるかもしれない。ロシアは政治,経済,軍事の面からばかり見られることが多いという著者が指摘している状況は,残念ながらソ連邦が崩壊した現在でも変わっていない。もっとロシアの豊かな精神文化に目を向けようではないかという著者の主張には共感するものが多い。ロシアで昔から大切に守られてきた聖なるイコンをいつの日かこの目で見てみたいと思う。
キリスト教と笑い
宮田光雄 著(岩波新書)¥550
 キリスト教に限らないが,本質的に宗教と「笑い」とは相容れないものというイメージがある。しかし著者は,決してキリスト教と「笑い」は無縁ではなく,聖書の中には「キリスト教的ユーモア」が息づいているとする。「神のユーモア」では大魚に飲み込まれたヨナの物語を取り上げ,「イエスのユーモア」を喜びと解放の言葉としてとらえている。時代が下って,使徒パウロ,宗教改革者ルター,20世紀最大の神学者カール・バルトもやはり「笑い」を持っていたというのだ。意外な視点が新鮮な本。
キリスト教に限らないが,本質的に宗教と「笑い」とは相容れないものというイメージがある。しかし著者は,決してキリスト教と「笑い」は無縁ではなく,聖書の中には「キリスト教的ユーモア」が息づいているとする。「神のユーモア」では大魚に飲み込まれたヨナの物語を取り上げ,「イエスのユーモア」を喜びと解放の言葉としてとらえている。時代が下って,使徒パウロ,宗教改革者ルター,20世紀最大の神学者カール・バルトもやはり「笑い」を持っていたというのだ。意外な視点が新鮮な本。
キリスト教ハンドブック
遠藤周作 編(三省堂)¥1,500
 本書は2部構成からなり,第1部では「キリスト教概論」として,キリスト教とは何か,聖書,教会とその歴史,キリスト教と生活が述べられる。第1部の前に置かれた故遠藤周作の「日本人と基督教」は,さすが日本を代表するキリスト教作家の筆と思わせる。第2部は「用語解説」で,五十音順にキリスト教関連用語が解説されている。コンパクトなハンドブックで,とくに「用語解説」はちょっとした調べものに便利である。
本書は2部構成からなり,第1部では「キリスト教概論」として,キリスト教とは何か,聖書,教会とその歴史,キリスト教と生活が述べられる。第1部の前に置かれた故遠藤周作の「日本人と基督教」は,さすが日本を代表するキリスト教作家の筆と思わせる。第2部は「用語解説」で,五十音順にキリスト教関連用語が解説されている。コンパクトなハンドブックで,とくに「用語解説」はちょっとした調べものに便利である。

