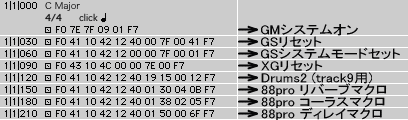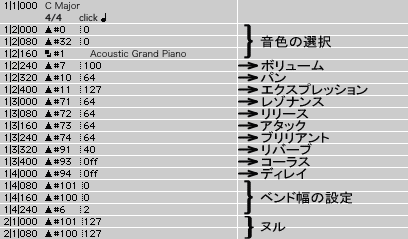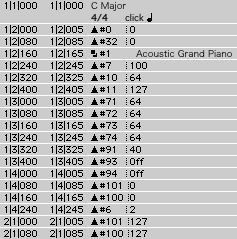TOP�@NO.1 |
| ��1��@�w�e���v���[�g����낤�x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@��P��ڂɂӂ��킵�����ǂ����킩��܂��AMIDI�f�[�^�𐧍삷��ۂɎ�ۂ悭��Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂́w�e���v���[�g�x����邱�Ƃ���n�߂����Ǝv���܂��B �@�e���v���[�g�����ɂ́A�{���g�p���鉹���łǂ̂悤�Ȑݒ肪�ł���̂��m���Ă����K�v������̂ł����A����������Ő������Ă��炱�̃e���v���[�g�����ƂȂ�ƁA���Ȃ��̘b�ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA�����ĂP��ڂɂ��̓��e�ōs���܂��B �@���āA���́w�e���v���[�g�x�ł����A���̂��߂̂��̂��A�܂��ǂ����ĕK�v�Ȃ̂��𗝉����܂��傤�B �@MIDI�f�[�^����낤�Ƃ��鎞�ɁA�K������ݒ肷����̂ɁA�e�g���b�N���Ƀ{�����[����p���A���F�̑I���Ȃǂ��Ȃ̖`���Ƀf�[�^���͂��Ă���Ǝv���܂��B�\�t�g�ɂ���Ă͎����I�ɐ���̃R���g���[���������̂�����܂����A����ȊO�ɏ�Ɏg�����͕̂ʓr���͂��Ă���ł��傤�B������R�}���h��I�����ē��͂����肷��̂́A���\��Ԃ̊|�����Ƃ��Ƃ͎v���܂��H �@�������悭�g�������̃f�[�^�����Ƃ��Ɠ����Ă���A�K�v�ȋ@�\�����G�f�B�b�g���Ă����邾���ō�ƌ������オ��܂��B���̂��߂ɁA���炩���߂��̂悤�ȃR���g���[������G�N�X�N���V�[�u�f�[�^�Ȃǂ��������f�[�^������Ă����A�V�����Ȃ̃f�[�^�́A���̃f�[�^���g���č�Ƃ��n�߂�悢�E�E�E�Ƃ������߂́w�e���v���[�g�f�[�^�x�Ȃ̂ł��B �@�Ȃ̖`���̐ݒ�ł悭�g�����̂ɁA���L�̂��̂�����܂��B �@�@�@�@�@���Z�b�g�p�G�N�X�N���V�[�u�f�[�^�@�i�G�N�X�N���V�[�u���͐�p�g���b�N�Ɂj �@�@�@�@�@�@�@�@�@F0 7E 7F 09 01 F7 �@�@�iGM�V�X�e���I���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7�@�@�iGS���Z�b�g�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@F0 41 10 42 12 00 00 7F 00 01 F7�@�@�iGS���[�h�Z�b�g MODE-1�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7 �@�@�iXG���Z�b�g�j �@�@�@�@�@���F�̑I���@�i�R�Z�b�g�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O�@�i�o���N�Z���N�g�j�@�@�@�����R�Q�@�i�}�b�v�Z���N�g�j�@�@�@PC�@�i�v���O�����`�F���W�j �@�@�@�@�@��{�ݒ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V�@�i�{�����[���j�@�@�@�����P�O�@�i�p���j�@�@�@�����P�P�@�i�G�N�X�v���b�V�����j �@�@�@�@�@���F�̃G�f�B�b�g �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V�P�@�i���]�i���X�j�@�@�@�����V�Q�@�i�����[�X�^�C���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V�R�@�i�A�^�b�N�^�C���j�@�@�@�����V�S�@�i�u���C�g�l�X�j �@�@�@�@�@�G�t�F�N�g�ݒ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����X�P�@�i���o�[�u�j�@�@�@�����X�R�@�i�R�[���X�j�@�@�@�����X�S�@�i�f�B���C�j �@�@�@�@�@���̑� �@�@�@�@�@�@�@�x���h���̐ݒ�@�i�R�Z�b�g�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�O�P�@�i�l�͂O�j�@�@�@�����P�O�O�@�i�l�͂O�j�@�@�@�����U�@�i�f�[�^�G���g���[�j �@�@�@�@�@�@�@�k���@�i�Q�Z�b�g�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�O�P�@�i�l�͂P�Q�V�j�@�@�@�����P�O�O�@�i�l�͂P�Q�V�j �@���������ۂɓ��͂������̂����}�̂��̂ł��B�����K�v�̂Ȃ����̂�����폜��������ł����A���ɕK�v�Ȃ��̂��o�Ă���Βlj���������̂ł��B�����̃f�[�^���Q���ߖڂ܂łɓ���A�R���ߖڂ���y�ȃf�[�^����͂��܂��傤�B �@�Ȃ��A�X�s�[�h�͂P���ڂ݂̂U�Obpm�ɂ��Ă���܂����A�G�N�X�N���V�[�u�f�[�^��ǂݍ��܂�����̂Q���ڂ���X�s�[�h��K�X�ݒ肵�܂��傤�B �@�܂��ŏ��ɃG�N�X�N���V�[�u�ł��B��{�I�ɂ͏�L�S�̃G�N�X�N���V�[�u���A���̏����̂܂ܓ��͂��܂��B���̏����́A�@�ǂ�ȉ����ł�GM�œ������@�A�BGS�����̂�GS���[�h�œ������@�CXG�����̂�XG���[�h�œ������@�Ƃ������̂ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�ǂ�ȉ����ł����̂S�̃f�[�^�����̏����œ��͂��Ă����Ζ��i�V�Ƃ������̂ł��B����GS������XG������GM���[�h�œ����������̂ł���A�A�B�C�̃f�[�^�͍폜���ĉ������B �@�c��̂S��GS�����p�ɓ��ꂽ���̂ł��̂ŁA�K�v�Ȃ���폜���ĉ������B�Ȃ��A�����̏ڂ�������͌�X�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B �@�����G�N�X�N���V�[�u�f�[�^�́A�P�`�����l���ɑ��낤���P�U�`�����l���ɑ��낤���S���ς�܂���B�܂�A�ǂ̃g���b�N�ɓ��͂��Ă��\��Ȃ��f�[�^�ł���̂ŁA�G�N�X�N���V�[�u��p�g���b�N������ē��͂��Ă����ƕ֗��ł��B
�@���Ȃ݂ɁA�P�����ŃG�N�X�N���V�[�u�𑗂�ݒ�����܂����̂ŁA�Q���ڂ����̓e���|���グ��悤�ɂ��Ă��܂��B�Q���ڈȍ~�ɃG�N�X�N���V�[�u��u���ꍇ�A�Ԋu�ɒ��ӂ��ĉ������B �@�Ȃ��A�Ȃ̐������e���|�͂Q���ڂŐݒ肷��悤�ɂ��ĉ������B �@���Ɋe�`�����l�����Ƃ̐ݒ����͂��܂��B�����ɂ͊�{�I�ɂ͏�L�̃G�N�X�N���V�[�u�ȊO�̂��̂���͂��܂��B �@�܂��P�g���b�N�ڂł��B�P���ڂɃG�N�X�N���V�[�u��u�����̂ŁA�Q���ڈȍ~�ɂ��ׂĂ�z�u���܂����B �@�e���v���[�g�p�ł��̂ŁA���ׂĉ����̃f�t�H���g�f�[�^�ɂȂ��Ă��܂��B������K�v�ɉ����ĕω������邱�ƂŁA���������R���g���[��������͂����Ԃ��Ȃ��܂��B�Ⴆ�����X�P�̓��o�[�u�ł����A�����̃f�t�H���g�l�͂S�O�ł��̂ŁA�e���v���[�g�ł��S�O�ł��B�����[���������Ȃ�S�O�ȏ�ɁA�������Ȃ�S�O�ȉ��ɕς��邾���ł����̂ł��B
�@�Ƃ������ƂŁA�����Ɏ��̍�����e���v���[�g�f�[�^��u���Ă����܂��B��������g���ɂȂ邩�A���邢�͂����g�̎g���₷���e���v���[�g�ɃG�f�B�b�g���ėL���ɂ��g���������B �@������ڂ�����������܂��̂ŁA������ҁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@template.lzh�i�P�U�`�����l���p�j�@�𓀂���Ɓutemplate.mid�v�ɂȂ�܂��B�@�i'05.11.09.�����Łj |