CD & Video for Easter
このページのBGMは,ShibataさんのMIDIで聴く「マタイ受難曲」から
バス・アリア 「われに返せ,わがイエスをば!」です。
*CD番号は私が買ったときのものです。購入される場合は必ずご自分でチェックしてください。
ドヴォルザーク:「スターバト・マーテル」
(Deutsche Gramophone 471 033-2)
 ドヴォルザークのスターバト・マーテルはCD2枚にわたる大作だ。声楽陣が合唱とソプラノ,メゾ・ソプラノ,テノール,バスの4人のソリストという編成も大きい。合唱が入るところは大変な熱気と迫力に包まれる部分が多いのだが,ドヴォルザークのメロディー・メーカーぶりはむしろゆったりしたテンポの曲でのソロやデュエットで発揮されている。管弦楽のボヘミアらしい土俗的な旋律も魅力的だ。この曲はペルゴレージはもちろんのことロッシーニのスターバト・マーテルよりも知られていないだろうが,第8曲のデュエットなど本当にジーンと来るいい音楽だ。
ドヴォルザークのスターバト・マーテルはCD2枚にわたる大作だ。声楽陣が合唱とソプラノ,メゾ・ソプラノ,テノール,バスの4人のソリストという編成も大きい。合唱が入るところは大変な熱気と迫力に包まれる部分が多いのだが,ドヴォルザークのメロディー・メーカーぶりはむしろゆったりしたテンポの曲でのソロやデュエットで発揮されている。管弦楽のボヘミアらしい土俗的な旋律も魅力的だ。この曲はペルゴレージはもちろんのことロッシーニのスターバト・マーテルよりも知られていないだろうが,第8曲のデュエットなど本当にジーンと来るいい音楽だ。
すでに亡き巨匠ジュゼッペ・シノーポリがこのような比較的マイナーな大曲を録音する気になったのは,彼がこの曲にオペラ的な熱いドラマを見ていたからではないだろうか。彼の意気に応えた合唱団は非常な熱演だし,伝統を誇るドレスデン・シュターカッペレの弦はふくよかによく歌う。
モンテヴェルディ:「聖母マリアの夕べの祈り」
(ARCHIV 429 566/7-2)
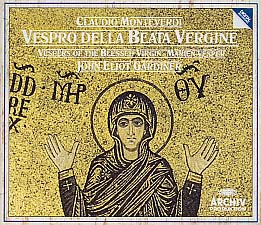 モンテヴェルディの「聖母マリアの夕べの祈り」は,その規模と内容からいってバッハ以前の最高の教会音楽の一つである。さらにイタリアが生み出した最高の教会音楽といってよいかもしれない。まず編成が巨大である。独唱者(ソプラノ,カウンターテノール,テノール,バス),合唱団,少年合唱団,オーケストラに加えてこのCDではコルネットのグループが賛助出演している。名曲はすべてそうだが,最初と最後がとくに印象的である。最初の「神よ,慈悲もてわれを助けたまえ」では,モンテヴェルディ自身のオペラ「オルフェオ」のファンファーレ風序曲トッカータが器楽声部に使われている。高音のコルネットの効果がめざましい。終わりの約20分にも及ぶ壮大なマニフィカトにはただただ圧倒される。その他の曲でも,フル編成のスケールが大きい曲あり,室内楽的で繊細な曲ありと,その変化は無限といってよく,教会音楽というよりは,波乱万丈のオペラを聴いている感さえする。CD2枚にもわたる長大な教会音楽でありながら,退屈な部分は全くない。
モンテヴェルディの「聖母マリアの夕べの祈り」は,その規模と内容からいってバッハ以前の最高の教会音楽の一つである。さらにイタリアが生み出した最高の教会音楽といってよいかもしれない。まず編成が巨大である。独唱者(ソプラノ,カウンターテノール,テノール,バス),合唱団,少年合唱団,オーケストラに加えてこのCDではコルネットのグループが賛助出演している。名曲はすべてそうだが,最初と最後がとくに印象的である。最初の「神よ,慈悲もてわれを助けたまえ」では,モンテヴェルディ自身のオペラ「オルフェオ」のファンファーレ風序曲トッカータが器楽声部に使われている。高音のコルネットの効果がめざましい。終わりの約20分にも及ぶ壮大なマニフィカトにはただただ圧倒される。その他の曲でも,フル編成のスケールが大きい曲あり,室内楽的で繊細な曲ありと,その変化は無限といってよく,教会音楽というよりは,波乱万丈のオペラを聴いている感さえする。CD2枚にもわたる長大な教会音楽でありながら,退屈な部分は全くない。
このCDは演奏の面でも記念碑的である。モンテヴェルディが楽長を務めたヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂において,英国の名指揮者ジョン・エリオット・ガーディナーが周到な準備のもと満を持して行ったライヴ・レコーディングだけに,そのエネルギッシュな迫力にはすさまじいものがある。この大聖堂のすばらしい残響もこの録音を成功に導いた大きな要因の一つだろう。
シュッツ:「シンフォニエ・サクレ」第2集
(CHACONNE CHAN 0566/7)
 シュッツといえば厳粛な教会合唱音楽の作曲家というイメージがあるが,実は彼は若いときにイタリアのヴェネツィアに留学して高名なジョバンニ・ガブリエリから当時の最先端のイタリアン・マドリガーレの技法を学んでいる。ドイツに帰国してからシュッツが進んだ道は,世俗的なイタリアン・マドリガーレではなく,ドイツ語によるプロテスタント教会音楽であったが,シュッツが学んだ「言葉を歌わせる」技法は教会音楽の中にも立派に生きている。この「シンフォニエ・サクレ」第2集は,テキストこそ聖書の福音書や詩篇だが,音楽はイタリアン・マドリガーレの伝統にそのままのっかったものといってよい。曲の編成はソプラノ,アルト,テノール,バスの独唱あるいは重唱(+弦の伴奏)といろいろであり,曲の雰囲気も変化に富んでいる。この曲集をはじめて聴いたとき合唱音楽以外のシュッツもいいなと思った。本当のことをいえば,私がこのCDを買った理由というのは,ソプラノをエマ・カークビーが歌っていることだった。やはり彼女の澄んだ歌声はバロックの曲では絶対的な強みを発揮してすばらしい。
シュッツといえば厳粛な教会合唱音楽の作曲家というイメージがあるが,実は彼は若いときにイタリアのヴェネツィアに留学して高名なジョバンニ・ガブリエリから当時の最先端のイタリアン・マドリガーレの技法を学んでいる。ドイツに帰国してからシュッツが進んだ道は,世俗的なイタリアン・マドリガーレではなく,ドイツ語によるプロテスタント教会音楽であったが,シュッツが学んだ「言葉を歌わせる」技法は教会音楽の中にも立派に生きている。この「シンフォニエ・サクレ」第2集は,テキストこそ聖書の福音書や詩篇だが,音楽はイタリアン・マドリガーレの伝統にそのままのっかったものといってよい。曲の編成はソプラノ,アルト,テノール,バスの独唱あるいは重唱(+弦の伴奏)といろいろであり,曲の雰囲気も変化に富んでいる。この曲集をはじめて聴いたとき合唱音楽以外のシュッツもいいなと思った。本当のことをいえば,私がこのCDを買った理由というのは,ソプラノをエマ・カークビーが歌っていることだった。やはり彼女の澄んだ歌声はバロックの曲では絶対的な強みを発揮してすばらしい。
リュリ:「テ・デウム」 他
(NAXOS 8.554397)
 フィレンツェ出身のイタリア人でありながら,太陽王「ルイ14世」の庇護のもと活躍したリュリはフランス・バロック期を代表するオペラ作曲家であった。残念ながら,彼が残したオペラの多くは再現が現在では難しいということもあって,ほとんど忘れ去られてしまっている。こうした問題が他の多くのバロック・オペラにも共通した問題である。英国びいきだからいうわけではないが,バロック・オペラとしては今日例外的に続々と新しい解釈,演奏が登場してくる「ディドーとエネアス」を書いたパーセルの偉大さ,その劇作品の時代を超えた普遍性が改めて思い起こされる。宗教作品は必ずしもリュリの本分ではなかったかもしれないが,この「テ・デウム」はオペラを得意としたリュリの面目が躍如とした明るく輝かしい作品である。シャルパンティエの「テ・デウム」で活躍するトランペットの代わりに,リュリの「テ・デウム」ではティンパニが活躍し,低音でドンドコ,ドンドコ鳴っているのが印象的。これらフランス・バロック期の代表的な2つの「テ・デウム」を聴き比べてみるのもおもしろい。他に収録されている「ミゼレーレ」と「手を打ち喜べ,ガリアの民よ」共に曲調の違いこそあれ,いずれの曲も大らかで屈託がない。シャルパンティエの音楽の方が音楽に変化があって私にはおもしろいが,太陽王はこういうリュリの安定した音楽を愛したのだろうか。
フィレンツェ出身のイタリア人でありながら,太陽王「ルイ14世」の庇護のもと活躍したリュリはフランス・バロック期を代表するオペラ作曲家であった。残念ながら,彼が残したオペラの多くは再現が現在では難しいということもあって,ほとんど忘れ去られてしまっている。こうした問題が他の多くのバロック・オペラにも共通した問題である。英国びいきだからいうわけではないが,バロック・オペラとしては今日例外的に続々と新しい解釈,演奏が登場してくる「ディドーとエネアス」を書いたパーセルの偉大さ,その劇作品の時代を超えた普遍性が改めて思い起こされる。宗教作品は必ずしもリュリの本分ではなかったかもしれないが,この「テ・デウム」はオペラを得意としたリュリの面目が躍如とした明るく輝かしい作品である。シャルパンティエの「テ・デウム」で活躍するトランペットの代わりに,リュリの「テ・デウム」ではティンパニが活躍し,低音でドンドコ,ドンドコ鳴っているのが印象的。これらフランス・バロック期の代表的な2つの「テ・デウム」を聴き比べてみるのもおもしろい。他に収録されている「ミゼレーレ」と「手を打ち喜べ,ガリアの民よ」共に曲調の違いこそあれ,いずれの曲も大らかで屈託がない。シャルパンティエの音楽の方が音楽に変化があって私にはおもしろいが,太陽王はこういうリュリの安定した音楽を愛したのだろうか。
ベートーヴェン:「荘厳ミサ曲」作品123
(EMI CDC 7 49950 2)
 ベートーヴェン晩年の大作であるにもかかわらず,第九交響曲と比べるとはるかに知名度は低く,演奏される機会も少ない。これは,宗教曲という曲の性格もあるし,第九交響曲の「歓喜の主題」のような分かりやすい名旋律がないということにもよるだろう。しかし,晩年のベートーヴェンを聴く上でやはりこの曲を避けて通るわけにはいかない。後期の弦楽四重奏曲の枯れた味わいとは違って,全体的に中期のベートーヴェンを思わせるような力強く輝かしい音が鳴り響いている。それが「荘厳」ということなのだろうが,私がこの曲を聴くたびに最も心を打たれるのは,第4曲「サンクトゥス」の天上的なヴァイオリン・ソロの響きである。テイト指揮のイギリス室内管弦楽団は,小編成の楽団ならではの引き締まった音を聴かせる。そしてホセ・ルイス・ガルシアのヴァイオリン・ソロは,決して甘くなく,それでいて音が艶やかである。ソリストと合唱団もテイトの意図を汲み,室内楽的にまとまった演奏を聴かせる。
ベートーヴェン晩年の大作であるにもかかわらず,第九交響曲と比べるとはるかに知名度は低く,演奏される機会も少ない。これは,宗教曲という曲の性格もあるし,第九交響曲の「歓喜の主題」のような分かりやすい名旋律がないということにもよるだろう。しかし,晩年のベートーヴェンを聴く上でやはりこの曲を避けて通るわけにはいかない。後期の弦楽四重奏曲の枯れた味わいとは違って,全体的に中期のベートーヴェンを思わせるような力強く輝かしい音が鳴り響いている。それが「荘厳」ということなのだろうが,私がこの曲を聴くたびに最も心を打たれるのは,第4曲「サンクトゥス」の天上的なヴァイオリン・ソロの響きである。テイト指揮のイギリス室内管弦楽団は,小編成の楽団ならではの引き締まった音を聴かせる。そしてホセ・ルイス・ガルシアのヴァイオリン・ソロは,決して甘くなく,それでいて音が艶やかである。ソリストと合唱団もテイトの意図を汲み,室内楽的にまとまった演奏を聴かせる。
ペルゴレージ:「スターバト・マーテル」 他
(RCA 09026-61215-2)
 私は「夭折の天才作曲家」という響きに弱くて,モーツァルト,シューベルト,メンデルスゾーンといった30代で世を去った作曲家に昔から惚れこんできた。そんな私がバース滞在中に偶然聴いた知られざる英国の天才作曲家トーマス・リンリー・Jr(1756-1778)をすぐ気に入ったのは当然である。当時の全欧的音楽シーンを見渡してみても,リンリーの残した作品が天才の霊感に満ち,22歳で没したという年齢を考えると驚くべき円熟に達しているのは間違いない。そして,イタリア生まれの作曲家ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ(1710-1736)は,リンリーより半世紀ほど前に生まれたやはり「20代で没した」天才作曲家である。もっとも,ペルゴレージの名前はリンリーとは比較にならないくらい昔から有名である。とくに,歌劇「奥様女中」やこの「スターバト・マーテル」によって。
私は「夭折の天才作曲家」という響きに弱くて,モーツァルト,シューベルト,メンデルスゾーンといった30代で世を去った作曲家に昔から惚れこんできた。そんな私がバース滞在中に偶然聴いた知られざる英国の天才作曲家トーマス・リンリー・Jr(1756-1778)をすぐ気に入ったのは当然である。当時の全欧的音楽シーンを見渡してみても,リンリーの残した作品が天才の霊感に満ち,22歳で没したという年齢を考えると驚くべき円熟に達しているのは間違いない。そして,イタリア生まれの作曲家ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ(1710-1736)は,リンリーより半世紀ほど前に生まれたやはり「20代で没した」天才作曲家である。もっとも,ペルゴレージの名前はリンリーとは比較にならないくらい昔から有名である。とくに,歌劇「奥様女中」やこの「スターバト・マーテル」によって。
元々「スターバト・マーテル」とは「悲しみの聖母」という日本名でも知られる韻文詩で,13世紀の修道士ヤコポーネ・ダ・トーディの作とされる。十字架の傍らにたたずむ悲しみの聖母マリアをうたったキリスト教文学の傑作であり,ルネサンス時代以降多くの作曲家がこの詩をもとに「スターバト・マーテル」を作曲した。その中でもペルゴレージの「スターバト・マーテル」は最高の作品と称えられる名作である。後年のロッシーニやドヴォルザークの作品に比べれば規模は小さく,弦楽オーケストラと2人の独唱(ソプラノ,アルト)のみの編成だが,音楽的な密度はすばらしく高い。ペルゴレージは原詩を12の部分に区切り,全12曲の構成としているが,暗く沈痛な曲と明るく軽やかな曲との対照が絶妙である。どの曲も旋律が美しいのでソプラノとアルトのオペラ・アリアを聴いているような感じがする。この曲の演奏の成否は大部分ソリストにかかっているといってよいが,このCDの目玉はアルトにドイツの名アルト,ナタリー・シュトゥッツマンを起用していることにある。ゆったりめのテンポにのってシュトゥッツマンの深々とした声が朗々と響くのをはじめて聴いたときには感動した。もう一曲アルトのための「サルヴェ・レジーナ」という15分ほどの佳品が入っており,この曲でもシュトゥッツマンの低音の魅力を味わえる。
ロッシーニ:「スターバト・マーテル」
(Deutsche Gramophone 449 178-2)
 ロッシーニといえば,いうまでもなく「セヴィリアの理髪師」や「ウィリアム・テル」で有名なイタリア・オペラの作曲家である。彼の「スターバト・マーテル」は60分近くの大曲で,編成もフル・オーケストラに合唱,4人のソリスト(ソプラノ2人,テノール,バス)と,ペルゴレージの曲に比べればはるかに大きい。歌詞のことなど知らずに聴けば,ロッシーニの曲,とくにソロやデュエットのアリアはイタリアン・カンタービレの連続で,宗教曲というよりはオペラそのものである。でも非常に美しい音楽であることにかわりはない。その中で宗教的雰囲気を感じさせる曲として,ア・カペラの合唱で歌われる第9曲"Quando corpus morietur"の静謐な美しさを特筆しておきたい。気鋭の韓国人指揮者チョン・ミュン・ファン指揮のウィーン・フィルハーモニーと国立歌劇場合唱団,ソプラノの名花チチェーリア・バルトリなど第一級の演奏陣だけに,その技術力と表現力,クライマックスでの迫力には圧倒される。
ロッシーニといえば,いうまでもなく「セヴィリアの理髪師」や「ウィリアム・テル」で有名なイタリア・オペラの作曲家である。彼の「スターバト・マーテル」は60分近くの大曲で,編成もフル・オーケストラに合唱,4人のソリスト(ソプラノ2人,テノール,バス)と,ペルゴレージの曲に比べればはるかに大きい。歌詞のことなど知らずに聴けば,ロッシーニの曲,とくにソロやデュエットのアリアはイタリアン・カンタービレの連続で,宗教曲というよりはオペラそのものである。でも非常に美しい音楽であることにかわりはない。その中で宗教的雰囲気を感じさせる曲として,ア・カペラの合唱で歌われる第9曲"Quando corpus morietur"の静謐な美しさを特筆しておきたい。気鋭の韓国人指揮者チョン・ミュン・ファン指揮のウィーン・フィルハーモニーと国立歌劇場合唱団,ソプラノの名花チチェーリア・バルトリなど第一級の演奏陣だけに,その技術力と表現力,クライマックスでの迫力には圧倒される。
ビーバー:「ロザリオのソナタ」
(Virgin Classics VCD 7 90838-2)
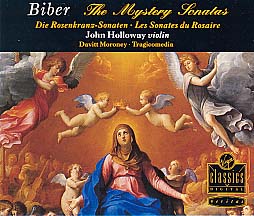 ここで私のとっておきの愛聴曲を。宗教画のジャケットと「ロザリオのソナタ」という曲名から教会音楽を想像されるかもしれないが,これは実はバロック時代のヴァイオリン・ソナタ集である。作者のビーバー(1644-1704)は,ボヘミアで生まれ,オーストリアのザルツブルクで活躍した作曲家兼ヴァイオリニスト。このソナタ集に「ロザリオのソナタ」というかわったタイトルがついているのは,16曲のソナタのそれぞれ(正確には終曲のパッサカリアを除く)に,新約聖書から取られた標題がつけられており,ロザリオ(カトリックで使う数珠)をまさぐりながら聖母マリアに祈るための標題音楽となっているからである。たとえば1曲目には「受胎告知」,11曲目には「キリストの復活」という標題がつけられている。この曲は当時のザルツブルクの大司教が創設した「ロザリオ信心会」あるいは大司教本人の依頼により作曲されたものと考えられている。
ここで私のとっておきの愛聴曲を。宗教画のジャケットと「ロザリオのソナタ」という曲名から教会音楽を想像されるかもしれないが,これは実はバロック時代のヴァイオリン・ソナタ集である。作者のビーバー(1644-1704)は,ボヘミアで生まれ,オーストリアのザルツブルクで活躍した作曲家兼ヴァイオリニスト。このソナタ集に「ロザリオのソナタ」というかわったタイトルがついているのは,16曲のソナタのそれぞれ(正確には終曲のパッサカリアを除く)に,新約聖書から取られた標題がつけられており,ロザリオ(カトリックで使う数珠)をまさぐりながら聖母マリアに祈るための標題音楽となっているからである。たとえば1曲目には「受胎告知」,11曲目には「キリストの復活」という標題がつけられている。この曲は当時のザルツブルクの大司教が創設した「ロザリオ信心会」あるいは大司教本人の依頼により作曲されたものと考えられている。
この曲のいわれもおもしろいが,曲の中味もそれに劣らずおもしろい。「ロザリオのソナタ」では,2曲を除いては通常の5度以外の調弦法であるスコルダトゥーラという特殊な調弦が用いられており,よく聴くと通常の奏法では聴けないような多様な音色が聴こえてくる。2枚組のCDで全曲を聴くと相当長いが,1曲1曲に当代随一のヴァイオリニストであったビーバーの技巧的工夫が感じられ,メロディーもなかなか美しい曲が多いから,ヴァイオリン音楽愛好者には非常に魅力のある作品なのである。とくに最初と最後のソナタはよい。第1曲「受胎告知」第2楽章「アリアと変奏」の美しさは短いけれども忘れがたいし,終曲の「パッサカリア」は後年の大バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」を予見させるかのような無伴奏ヴァイオリンによる充実した変奏曲である。演奏者のジョン・ホロウェイはロンドンで活躍しているバロック・ヴァイオリンの奏者で,この作品では技巧よりも抒情を重視した演奏を聴かせる。ヴィオラ・ダ・ガンバ,リュート,ハープ,オルガンなどの伴奏(通奏低音)も美しい。この盤は1990年の英国"The Gramophone Awards"を受賞した。
シャルパンティエ:「テ・デウム」,「聖母被昇天のミサ」 他
(harmonia mundi HMC 901298)
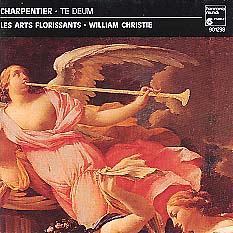 シャルパンティエ(1643-1704)がフランス・バロック屈指のメロディー・メーカーであることは私がクリスマスの教会音楽のページでさんざん強調した通り。「テ・デウム」はシャルパンティエの数ある教会音楽の中でも最も華麗で力強い作品である。オーケストラと独唱,合唱による大規模な編成の作品。オーケストラによる「前奏曲」は冒頭の金管による主題がとくに有名で,テレビ番組にもしばしば使われる。たしかこの曲を使ったCMも昔あったのでは。ともかく,いかにも「王宮」といった雰囲気のある曲である。それで「テ・デウム」が派手なだけの曲かといえばさにあらず。しみじみとした独唱や美しい器楽伴奏もある変化に富んだ名作なのである。他に収録された2曲もシャルパンティエの音楽の美しさを味わえるものばかり。シャルパンティエ・リヴァイヴァルをはたしたウィリアム・クリスティー指揮レザール・フロリサンの洒脱な名演奏で。
シャルパンティエ(1643-1704)がフランス・バロック屈指のメロディー・メーカーであることは私がクリスマスの教会音楽のページでさんざん強調した通り。「テ・デウム」はシャルパンティエの数ある教会音楽の中でも最も華麗で力強い作品である。オーケストラと独唱,合唱による大規模な編成の作品。オーケストラによる「前奏曲」は冒頭の金管による主題がとくに有名で,テレビ番組にもしばしば使われる。たしかこの曲を使ったCMも昔あったのでは。ともかく,いかにも「王宮」といった雰囲気のある曲である。それで「テ・デウム」が派手なだけの曲かといえばさにあらず。しみじみとした独唱や美しい器楽伴奏もある変化に富んだ名作なのである。他に収録された2曲もシャルパンティエの音楽の美しさを味わえるものばかり。シャルパンティエ・リヴァイヴァルをはたしたウィリアム・クリスティー指揮レザール・フロリサンの洒脱な名演奏で。
ブルックナー:「ミサ曲第2番 ホ短調」,「モテット集」
(SONY SRCR 8878)
 中世,ルネサンス,古典派,ロマン派と時代が下るにつれ,全音楽に占める教会音楽の割合は減る一方。もちろんこれはキリスト教会の影響力の衰微が影響しているのだが,とくにロマン派の時代には教会音楽に真剣に取り組んだ大作曲家は少ない。ブルックナーはその中の数少ない大作曲家の一人であった。リンツ大聖堂のオルガニストであったブルックナーの大交響曲にはオルガンの響きがするとよくいわれるように,ブルックナーの耳にはいつも大聖堂のオルガンと合唱の響きが聴こえていたに違いない。だから「ミサ曲」や「モテット」を作曲することは,ブルックナーにとっては全く不自然ではなかったに違いない。管楽器のみのオーケストラが控えめに加わる「ミサ曲第2番」の美しいハーモニー,合唱のみの「モテット集」の純粋な響きともに,ブルックナーにこれほど美しい教会音楽があるとはこのCDを聴くまで私は知らなかった。モテットの中では,「ブルックナーのアヴェ・マリア」として知られる7声の「アヴェ・マリア」が神々しい美しさで出色。フリーダー・ベルニウス指揮のシュトウットガルト室内合唱団の合唱は甘さを排した厳しいものであるが,それでいてふっくらとした豊かなハーモニーが耳に心地よい。
中世,ルネサンス,古典派,ロマン派と時代が下るにつれ,全音楽に占める教会音楽の割合は減る一方。もちろんこれはキリスト教会の影響力の衰微が影響しているのだが,とくにロマン派の時代には教会音楽に真剣に取り組んだ大作曲家は少ない。ブルックナーはその中の数少ない大作曲家の一人であった。リンツ大聖堂のオルガニストであったブルックナーの大交響曲にはオルガンの響きがするとよくいわれるように,ブルックナーの耳にはいつも大聖堂のオルガンと合唱の響きが聴こえていたに違いない。だから「ミサ曲」や「モテット」を作曲することは,ブルックナーにとっては全く不自然ではなかったに違いない。管楽器のみのオーケストラが控えめに加わる「ミサ曲第2番」の美しいハーモニー,合唱のみの「モテット集」の純粋な響きともに,ブルックナーにこれほど美しい教会音楽があるとはこのCDを聴くまで私は知らなかった。モテットの中では,「ブルックナーのアヴェ・マリア」として知られる7声の「アヴェ・マリア」が神々しい美しさで出色。フリーダー・ベルニウス指揮のシュトウットガルト室内合唱団の合唱は甘さを排した厳しいものであるが,それでいてふっくらとした豊かなハーモニーが耳に心地よい。
アッレーグリ:「ミゼレーレ」/パレストリーナ:「教皇マルチェルスのミサ曲」 他
(Gimell CDGIM339)
 アッレーグリ(1582-1652)の「ミゼレーレ」がなんといっても聴きもの。少年モーツァルトがローマを訪れたとき,門外不出の秘曲とされ楽譜が公開されていなかったこの曲を一度聴いただけですべて楽譜に書き写してしまったというエピソードで有名な曲である。天才モーツァルトと違って,普通の人が一度聴いただけでこの曲を覚えるのは不可能であろうが,一度聴いたら忘れられない美しい曲であるのは確かであろう。何といっても曲の冒頭が印象的である。おそらくアッレーグリは,「ミゼレーレ」冒頭の憂いを帯びた名旋律を残したおかげで,音楽史に名前を残したのだ。この曲は昔はイースターに先立つ聖週間の水曜日から金曜日にかけてバチカンのシスティーナ礼拝堂で行われる典礼でしか聴くことができなかったらしいから,本当に秘曲中の秘曲だったのである。タリス・スコラーズの初録音(1980年)であるこのCDのおかげで,好きなときにいつでも「ミゼレーレ」を聴くことができるのはありがたいことだ。パレストリーナの「教皇マルチェルスのミサ曲」も入っているが,パレストリーナの曲としては,「聖母被昇天のミサ」の方が私にはおもしろい。それよりはむしろ,もう一曲入っている作品で,英国の作曲家ウィリアム・マンディー(c.1529-1591)の「天の父の声は」が変化に富んだ力強い作品で楽しめる。
アッレーグリ(1582-1652)の「ミゼレーレ」がなんといっても聴きもの。少年モーツァルトがローマを訪れたとき,門外不出の秘曲とされ楽譜が公開されていなかったこの曲を一度聴いただけですべて楽譜に書き写してしまったというエピソードで有名な曲である。天才モーツァルトと違って,普通の人が一度聴いただけでこの曲を覚えるのは不可能であろうが,一度聴いたら忘れられない美しい曲であるのは確かであろう。何といっても曲の冒頭が印象的である。おそらくアッレーグリは,「ミゼレーレ」冒頭の憂いを帯びた名旋律を残したおかげで,音楽史に名前を残したのだ。この曲は昔はイースターに先立つ聖週間の水曜日から金曜日にかけてバチカンのシスティーナ礼拝堂で行われる典礼でしか聴くことができなかったらしいから,本当に秘曲中の秘曲だったのである。タリス・スコラーズの初録音(1980年)であるこのCDのおかげで,好きなときにいつでも「ミゼレーレ」を聴くことができるのはありがたいことだ。パレストリーナの「教皇マルチェルスのミサ曲」も入っているが,パレストリーナの曲としては,「聖母被昇天のミサ」の方が私にはおもしろい。それよりはむしろ,もう一曲入っている作品で,英国の作曲家ウィリアム・マンディー(c.1529-1591)の「天の父の声は」が変化に富んだ力強い作品で楽しめる。
パレストリーナ:「聖母被昇天のミサ」 他
(Gimell CDGIM020)
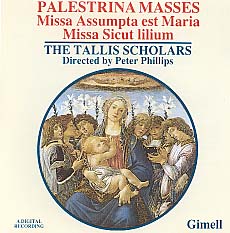 ルネサンス後期にローマで活躍したパレストリーナ(1525-1594)は,いわゆるローマ教皇庁のお抱え作曲家であった。よくも悪くもパレストリーナの音楽には,盛期ルネサンスの時代も過ぎ去り,ジョスカン・デ・プレに見られたような調和と均衡の世界が崩れて,それでもギリギリのところで踏みとどまっているようなところがある。ルネサンス・ポリフォニーの残光が輝いているといったらよいのであろうか。彼の音楽は人工的だといって嫌う人もいるけれど,一方で非常に美しく,美の楽園に居るような法悦境に至らせてくれるのも事実。この「聖母被昇天のミサ」も,官能的といってもよいハーモニーの美しさにどっぷりと浸らせてくれる作品である。タリス・スコラーズの一糸乱れぬ歌いぶりはいつもながら見事。1991年の英国"The Gramophone Awards"を受賞した名盤である。
ルネサンス後期にローマで活躍したパレストリーナ(1525-1594)は,いわゆるローマ教皇庁のお抱え作曲家であった。よくも悪くもパレストリーナの音楽には,盛期ルネサンスの時代も過ぎ去り,ジョスカン・デ・プレに見られたような調和と均衡の世界が崩れて,それでもギリギリのところで踏みとどまっているようなところがある。ルネサンス・ポリフォニーの残光が輝いているといったらよいのであろうか。彼の音楽は人工的だといって嫌う人もいるけれど,一方で非常に美しく,美の楽園に居るような法悦境に至らせてくれるのも事実。この「聖母被昇天のミサ」も,官能的といってもよいハーモニーの美しさにどっぷりと浸らせてくれる作品である。タリス・スコラーズの一糸乱れぬ歌いぶりはいつもながら見事。1991年の英国"The Gramophone Awards"を受賞した名盤である。
ユビラーテ・デオ(16,17世紀のモテット集)
(Deutsche Schallplatten TKCC-70289)
 東西ドイツが劇的に統合したときには,多くの人が拍手をもってこれを迎えたが,今なお東西の経済力や社会資本には大きな格差があるようだ。統合前の東ドイツは国威発揚の手段としてオリンピックに力を入れ,強化選手(とくに男まさりの女子選手)がたくさんの金メダルを獲得したが,少なからずの選手がドーピングをしていたのではないかという疑惑が統合後に浮上したりして,経済面のみならず文化面でも旧東ドイツの評判は一時期さんざんであった。しかし音楽に関する限りは,旧東ドイツがドイツ音楽の正統的な演奏の伝統を脈々と受け継いできたことを誰も否定することはできない。オーケストラでいえばドレスデン・シュターッカペレのいぶし銀と評されるすばらしい音色。カール・ズスケ率いるベルリン弦楽四重奏団のベートーヴェンは質実剛健で感動的だったし,そして何よりも多くの世界的な歌手を輩出してきた。
東西ドイツが劇的に統合したときには,多くの人が拍手をもってこれを迎えたが,今なお東西の経済力や社会資本には大きな格差があるようだ。統合前の東ドイツは国威発揚の手段としてオリンピックに力を入れ,強化選手(とくに男まさりの女子選手)がたくさんの金メダルを獲得したが,少なからずの選手がドーピングをしていたのではないかという疑惑が統合後に浮上したりして,経済面のみならず文化面でも旧東ドイツの評判は一時期さんざんであった。しかし音楽に関する限りは,旧東ドイツがドイツ音楽の正統的な演奏の伝統を脈々と受け継いできたことを誰も否定することはできない。オーケストラでいえばドレスデン・シュターッカペレのいぶし銀と評されるすばらしい音色。カール・ズスケ率いるベルリン弦楽四重奏団のベートーヴェンは質実剛健で感動的だったし,そして何よりも多くの世界的な歌手を輩出してきた。
前置きが長くなってしまったが,本CDのDeutsche Schallplattenは旧東ドイツの代表的レーベルとして,派手さはないが優れたアルバムをリリースしてきた。このアルバムで歌っている合唱団は,史上最高のバッハ指揮者カール・リヒター,世界を代表する名歌手のペーター・シュライヤーテオ・アーダムが所属していた名門中の名門ドレスデンの聖十字架合唱団である。指揮は合唱指揮者として名高いマルティン・フレーミヒ。1986年という東西統合前の録音であるが,その合唱技術のすばらしさはもちろんのこと,選曲のすばらしさにもうならされる。収録されているのは,16〜17世紀につくられた長くてもせいぜい数分の短いモテットが14曲である。ハインリヒ・シュッツ(1585-1672)やハンス・レーオ・ハスラー(1564-1612)をはじめとするドイツの作曲家による作品が中心で,イタリアのジョバーンニ・ガブリエーリ(1554/57-1612)やアレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)の曲も入っている。ドイツの教会合唱音楽というと,もう少し後のJ・S・バッハの作品が圧倒的に有名だけれども,バッハよりも前にも優れた合唱作品がたくさんあるということを実感できるアルバム。私がとくにお気に入りの曲はザームエル・シャイト(1587-1654)の「ふたりのセラピム互いに呼びかわして」という曲。文字通り呼びかわしているかのような合唱と低音のオルガンが非常に印象的。
ジョスカン・デ・プレ:「ミサ・パンジェ・リングァ」 他
(Gimell CDGIM009)
 イギリス最高のコーラス・グループとして,1980年代から1990年代にかけて,ルネサンス期の教会音楽をテーマに活発な活動を続けたタリス・スコラーズの数多い録音の中でも屈指の名盤。古楽のCDとして初めて英国Gramophone誌の最優秀レコード賞を受賞した(1987)。このCDによってルネサンス・フランドル楽派の音楽の素晴らしさに目を見開かされた人も多いことだろう。私もその一人だが,このCDを聴いた友人からは例外なく感嘆の声があがった。「パンジェ・リングァ」とは「舌よ,歌え」の意味で,グレゴリオ聖歌の有名な定旋律である。ジョスカンは,この定旋律冒頭の「ミ−ミ−ファ−ミ」の音型を繰り返しミサの各曲で使っているのだが,この一度聴いたら忘れられない印象深い音型に加えて,各声部が絡み合うポリフォーニーの美しさには陶然とさせられる。すべてが完璧に調和したルネサンス合唱音楽のひとつの精華といってよいだろう。他に同じジョスカンの「ミサ・ラ・ソル・ファ・ミ・レ」を収録。タイトル通り音階唱法によって歌われるミサ曲だが,こちらも美しい曲である。謎に包まれたフランドル楽派最大の作曲家ジョスカン・デ・プレの生涯について知りたい方には,今谷和徳 著の「ルネサンスの音楽家たち I」(東京書籍)をお薦めする。
イギリス最高のコーラス・グループとして,1980年代から1990年代にかけて,ルネサンス期の教会音楽をテーマに活発な活動を続けたタリス・スコラーズの数多い録音の中でも屈指の名盤。古楽のCDとして初めて英国Gramophone誌の最優秀レコード賞を受賞した(1987)。このCDによってルネサンス・フランドル楽派の音楽の素晴らしさに目を見開かされた人も多いことだろう。私もその一人だが,このCDを聴いた友人からは例外なく感嘆の声があがった。「パンジェ・リングァ」とは「舌よ,歌え」の意味で,グレゴリオ聖歌の有名な定旋律である。ジョスカンは,この定旋律冒頭の「ミ−ミ−ファ−ミ」の音型を繰り返しミサの各曲で使っているのだが,この一度聴いたら忘れられない印象深い音型に加えて,各声部が絡み合うポリフォーニーの美しさには陶然とさせられる。すべてが完璧に調和したルネサンス合唱音楽のひとつの精華といってよいだろう。他に同じジョスカンの「ミサ・ラ・ソル・ファ・ミ・レ」を収録。タイトル通り音階唱法によって歌われるミサ曲だが,こちらも美しい曲である。謎に包まれたフランドル楽派最大の作曲家ジョスカン・デ・プレの生涯について知りたい方には,今谷和徳 著の「ルネサンスの音楽家たち I」(東京書籍)をお薦めする。
ブクステフーデ:オルガン名曲集
(ROMANESCA KICC 183)
 いつも教会音楽の伴奏役に回っているオルガンだが,バロック時代のとくに北ヨーロッパではオルガン・ソロの名曲がたくさん生まれて,この楽器にとって最も輝かしい時代を迎えた。J・S・バッハのオルガン曲はバロックのオルガン曲の集大成といってよいだろう。そのバッハの先輩にあたり,北ドイツのリューベックで活躍したディートリヒ・ブクステフーデの名声は今日より当時の方が高かったかもしれない。なにしろ彼のオルガン・コンサートの評判は遥か遠方までに及び,若き日のバッハが自分の職務を放り出し,中部ドイツのアルンシュタットからリューベックまではるばる徒歩でブクステフーデの演奏を聴きに行き大感激したというのは有名な逸話である。とにかくブクステフーデのオルガン曲は雄大で華麗。鍵盤,ペダルをフルに使ったすごい迫力のある曲がたくさんある。一方で,ドイツ・プロテスタント教会のコラールを主題にしたゆったりとした情感豊かな曲もあり,音楽の幅が広い。後者の部類に入る「いかに美しきかな,暁の明星は」(CDの和訳通り)は,ブクステフーデのオルガン曲で最も有名な曲であり,主題の美しさと充実した変奏がすばらしい。もしかしたら,バッハもブクステフーデのこの曲の演奏を聴いて,同じ主題を用いたカンタータ第1番「輝く曙の明星のいと美しきかな」の作曲を思い立ったのかもしれない。もうひとつ,このCDで特筆したいのは,ブクステフーデが活躍していた当時最高のオルガン製作者と謳われたアルプ・シュニットガーが作った世界でも三本指に入る名オルガン(ドイツ,ノルデン市ルトゲリ教会)が録音に用いられていることである。このオルガンを弾いているのはバッハ・コレギウム・ジャパンを率いる日本の鈴木雅明。深々としているが透明でクリアーなオルガンの音色を聴き,CDカバーのオルガンの美しい写真を見ると,ノルデンというドイツの田舎町に一度行ってみたくなる。
いつも教会音楽の伴奏役に回っているオルガンだが,バロック時代のとくに北ヨーロッパではオルガン・ソロの名曲がたくさん生まれて,この楽器にとって最も輝かしい時代を迎えた。J・S・バッハのオルガン曲はバロックのオルガン曲の集大成といってよいだろう。そのバッハの先輩にあたり,北ドイツのリューベックで活躍したディートリヒ・ブクステフーデの名声は今日より当時の方が高かったかもしれない。なにしろ彼のオルガン・コンサートの評判は遥か遠方までに及び,若き日のバッハが自分の職務を放り出し,中部ドイツのアルンシュタットからリューベックまではるばる徒歩でブクステフーデの演奏を聴きに行き大感激したというのは有名な逸話である。とにかくブクステフーデのオルガン曲は雄大で華麗。鍵盤,ペダルをフルに使ったすごい迫力のある曲がたくさんある。一方で,ドイツ・プロテスタント教会のコラールを主題にしたゆったりとした情感豊かな曲もあり,音楽の幅が広い。後者の部類に入る「いかに美しきかな,暁の明星は」(CDの和訳通り)は,ブクステフーデのオルガン曲で最も有名な曲であり,主題の美しさと充実した変奏がすばらしい。もしかしたら,バッハもブクステフーデのこの曲の演奏を聴いて,同じ主題を用いたカンタータ第1番「輝く曙の明星のいと美しきかな」の作曲を思い立ったのかもしれない。もうひとつ,このCDで特筆したいのは,ブクステフーデが活躍していた当時最高のオルガン製作者と謳われたアルプ・シュニットガーが作った世界でも三本指に入る名オルガン(ドイツ,ノルデン市ルトゲリ教会)が録音に用いられていることである。このオルガンを弾いているのはバッハ・コレギウム・ジャパンを率いる日本の鈴木雅明。深々としているが透明でクリアーなオルガンの音色を聴き,CDカバーのオルガンの美しい写真を見ると,ノルデンというドイツの田舎町に一度行ってみたくなる。
ヴィヴァルディ:「グローリア」/ヘンデル「ユトレヒト・テ・デウム&ユビラーテ」
(L'oiseau-Lyre 443 178-2)
 ヴィヴァルディといえば「四季」や「海の嵐」といった協奏曲に代表される器楽曲が圧倒的に有名で,彼の声楽曲はあまり知られていない。ところが多作家のヴィヴァルディのこと,声楽曲もたくさん残したらしい。このCDに入ってる「グローリア」はヴィヴァルディの最も有名な声楽曲で,「四季」の作曲家らしい華やかで明るい作品である。器楽曲を得意としたヴィヴァルディだけあって,オーケストラの動きも充実しており,合唱や独唱と十分以上に張り合っている。合唱も充実しているが,やはりこの曲の聴きどころは,ソプラノとアルトのアリアであろう。とくに,第3曲"Laudamus te"のソプラノ・デュオでは,ソプラノの一人がエマ・カークビーであるだけに,一層曲が輝きを増して聴こえる。ヘンデルの「ユトレヒト・テ・デウム&ユビラーテ」は,ヴィヴァルディの曲より規模が大きく,独唱にもソプラノのほかにカウンターテナー,テナー,バスが加わる。やはりイタリア人とドイツ人の違いなのか,ヘンデルの曲は明るいといってもヴィヴァルディの「グローリア」より大分陰りがある。そして,オーケストラの伴奏はより繊細で,オーボエやフルートのソロが効果的に使われている。ユビラーテ第3曲のカウンターテナーとバスのデュオなんかしみじみ聴かせるねえ。やっぱり声楽曲に関してはオペラの作曲で鍛えたヘンデルが一枚上手か!
ヴィヴァルディといえば「四季」や「海の嵐」といった協奏曲に代表される器楽曲が圧倒的に有名で,彼の声楽曲はあまり知られていない。ところが多作家のヴィヴァルディのこと,声楽曲もたくさん残したらしい。このCDに入ってる「グローリア」はヴィヴァルディの最も有名な声楽曲で,「四季」の作曲家らしい華やかで明るい作品である。器楽曲を得意としたヴィヴァルディだけあって,オーケストラの動きも充実しており,合唱や独唱と十分以上に張り合っている。合唱も充実しているが,やはりこの曲の聴きどころは,ソプラノとアルトのアリアであろう。とくに,第3曲"Laudamus te"のソプラノ・デュオでは,ソプラノの一人がエマ・カークビーであるだけに,一層曲が輝きを増して聴こえる。ヘンデルの「ユトレヒト・テ・デウム&ユビラーテ」は,ヴィヴァルディの曲より規模が大きく,独唱にもソプラノのほかにカウンターテナー,テナー,バスが加わる。やはりイタリア人とドイツ人の違いなのか,ヘンデルの曲は明るいといってもヴィヴァルディの「グローリア」より大分陰りがある。そして,オーケストラの伴奏はより繊細で,オーボエやフルートのソロが効果的に使われている。ユビラーテ第3曲のカウンターテナーとバスのデュオなんかしみじみ聴かせるねえ。やっぱり声楽曲に関してはオペラの作曲で鍛えたヘンデルが一枚上手か!
ハイドン:弦楽四重奏曲「十字架上の七つの言葉」
(NAXOS 8.550346)
 「弦楽四重奏曲」という言葉がなかったら,教会音楽だと思われてしまいそうだが,この曲に声は全く入っていない。純然たる「弦楽四重奏曲」である。原題は"Die sieben letzten Worte Jesu Christi"であるから,直訳すると「イエス・キリストの最後の七つの言葉」となる。ゴルゴダの丘で十字架にかけられたイエスの最後の言葉七つ(聖書のマタイ,ルカ,ヨハネの福音書が底本になっている)をモチーフにした七曲のソナタと,最初の序奏,最後の「地震」からなる全9曲の大曲である。演奏時間は50分以上を要し,ハイドンの弦楽四重奏曲としては最長である。しかし,タイトルから重く暗い曲ばかりを想像していると,それは全く違うことに気づかされる。むしろ,ハイドンの「普通」の弦楽四重奏曲よりも第1ヴァイオリンがよく歌う美しいカンタービレがたっぷり聴ける。ソナタ2の「はっきり言っておくが,あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」の情緒纏綿としたヴァイオリン・ソロはセレナードといった感じがする。私がいちばん好きなのは,ソナタ3「婦人よ,御覧なさい。あなたの子です。(弟子よ,)見なさい。あなたの母です。」の本当に優しさと安らぎに満ちた音楽。器楽曲といっても,ハイドンはやはり敬虔な気持ちで作曲に取り組んだのではないだろうか。晩年の「五度」や「日の出」といった名作四重奏曲とはまた違った魅力のあるハイドン中期の隠れた傑作である。
「弦楽四重奏曲」という言葉がなかったら,教会音楽だと思われてしまいそうだが,この曲に声は全く入っていない。純然たる「弦楽四重奏曲」である。原題は"Die sieben letzten Worte Jesu Christi"であるから,直訳すると「イエス・キリストの最後の七つの言葉」となる。ゴルゴダの丘で十字架にかけられたイエスの最後の言葉七つ(聖書のマタイ,ルカ,ヨハネの福音書が底本になっている)をモチーフにした七曲のソナタと,最初の序奏,最後の「地震」からなる全9曲の大曲である。演奏時間は50分以上を要し,ハイドンの弦楽四重奏曲としては最長である。しかし,タイトルから重く暗い曲ばかりを想像していると,それは全く違うことに気づかされる。むしろ,ハイドンの「普通」の弦楽四重奏曲よりも第1ヴァイオリンがよく歌う美しいカンタービレがたっぷり聴ける。ソナタ2の「はっきり言っておくが,あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる」の情緒纏綿としたヴァイオリン・ソロはセレナードといった感じがする。私がいちばん好きなのは,ソナタ3「婦人よ,御覧なさい。あなたの子です。(弟子よ,)見なさい。あなたの母です。」の本当に優しさと安らぎに満ちた音楽。器楽曲といっても,ハイドンはやはり敬虔な気持ちで作曲に取り組んだのではないだろうか。晩年の「五度」や「日の出」といった名作四重奏曲とはまた違った魅力のあるハイドン中期の隠れた傑作である。
セント・ポール大聖堂の賛美歌名曲集
(HYPERION CDH55036)
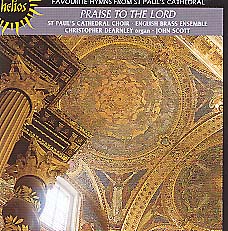 このCDでは,英国国教会の讃美歌16曲が名門セント・ポール大聖堂聖歌隊によって歌われている。国教会の賛美歌にはNEH(The New English Hymal)という番号がついている。(クリスマス・キャロル以外はあまり日本でなじみのない英国国教会の賛美歌を聴く上で,英国滞在時に国教会の讃美歌集を求めなかったのは失敗だった。いったい全部で何曲くらいあって,どういう分類がされているのだろうか。)収録されている16曲の賛美歌は,おそらく数多い賛美歌の中でも名の知れた名曲ばかりなのだろう。とにかくどの曲もメロディーが美しく印象的である。アルバムのタイトルにもなっている"Praise to the Lord(全能なる主をほめたたえよ)"(NEH440)のように,ブラス・アンサンブルも入った明るく輝かしい曲もあれば,"There is a green hill far away(はるかなる緑の丘)"(NEH92)のように伴奏なしでしみじみと歌われる曲もある。上の2曲もいいが,"Dear Lord and Father of mankind(人々の父である主よ)"(NEH353)や,"Lord Jesus think on me(主イエスはわれを忘れず)"(NEH70)の慈愛に満ちたやさしい調べが心に残る。
このCDでは,英国国教会の讃美歌16曲が名門セント・ポール大聖堂聖歌隊によって歌われている。国教会の賛美歌にはNEH(The New English Hymal)という番号がついている。(クリスマス・キャロル以外はあまり日本でなじみのない英国国教会の賛美歌を聴く上で,英国滞在時に国教会の讃美歌集を求めなかったのは失敗だった。いったい全部で何曲くらいあって,どういう分類がされているのだろうか。)収録されている16曲の賛美歌は,おそらく数多い賛美歌の中でも名の知れた名曲ばかりなのだろう。とにかくどの曲もメロディーが美しく印象的である。アルバムのタイトルにもなっている"Praise to the Lord(全能なる主をほめたたえよ)"(NEH440)のように,ブラス・アンサンブルも入った明るく輝かしい曲もあれば,"There is a green hill far away(はるかなる緑の丘)"(NEH92)のように伴奏なしでしみじみと歌われる曲もある。上の2曲もいいが,"Dear Lord and Father of mankind(人々の父である主よ)"(NEH353)や,"Lord Jesus think on me(主イエスはわれを忘れず)"(NEH70)の慈愛に満ちたやさしい調べが心に残る。
ウェストミンスター大聖堂合唱団の音楽
(HYPERION WCC100)
 1903年に創設以来,輝かしい足跡を残してきたウェストミンスター大聖堂合唱団がHYPERIONに録音した数多くの盤から編集されたベストアルバム。廉価盤でしかも80分近くも収録されているという大変お買得なアルバム。演奏はもちろんすばらしいうえに,しかもHYPERIONらしく選曲がなかなか凝っている。イギリス物一辺倒のプログラムではなく,メシアン,プーランクのようなフランスの20世紀の作品も入っている。イギリスの作品でも,ルネサンス期のバード,タイから,近現代のエルガー,スタンフォード,ブリテン,ホルストまで実に多彩。バードの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とタイの「もろもろの民よ」を除けば初めて聴く曲ばかりだったが,変化に富むプログラムが実に楽しい。CD最初のエルガー「偉大なる主」のちょっと陰りのあるロマンティックな味わいはいかにも彼の曲らしく,最後のスタンフォード「二重合唱のためのマニフィカト」は擬ルネサンス的で透明なハーモニーに19世紀的なロマンティシズムが息づく佳曲。なんだかんだいって,最初と最後に近代イギリスの大家の作品を持ってきたところに,イギリスのレーベルであるHYPERIONの誇りが感じられはしないだろうか。
1903年に創設以来,輝かしい足跡を残してきたウェストミンスター大聖堂合唱団がHYPERIONに録音した数多くの盤から編集されたベストアルバム。廉価盤でしかも80分近くも収録されているという大変お買得なアルバム。演奏はもちろんすばらしいうえに,しかもHYPERIONらしく選曲がなかなか凝っている。イギリス物一辺倒のプログラムではなく,メシアン,プーランクのようなフランスの20世紀の作品も入っている。イギリスの作品でも,ルネサンス期のバード,タイから,近現代のエルガー,スタンフォード,ブリテン,ホルストまで実に多彩。バードの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とタイの「もろもろの民よ」を除けば初めて聴く曲ばかりだったが,変化に富むプログラムが実に楽しい。CD最初のエルガー「偉大なる主」のちょっと陰りのあるロマンティックな味わいはいかにも彼の曲らしく,最後のスタンフォード「二重合唱のためのマニフィカト」は擬ルネサンス的で透明なハーモニーに19世紀的なロマンティシズムが息づく佳曲。なんだかんだいって,最初と最後に近代イギリスの大家の作品を持ってきたところに,イギリスのレーベルであるHYPERIONの誇りが感じられはしないだろうか。
ギリシャ正教の聖歌(聖ヨハネ・クリソストムの聖体礼儀)
(OPUS 30-78)
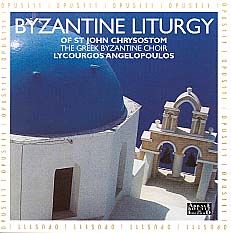 私は前からギリシャ正教の音楽に興味があった。遠い昔ビザンツ(東ローマ)帝国で栄えた東方教会の音楽とはどのようなものだったのか…。そのギリシャ正教の音楽の魅力をはじめて教えてくれたのがこのCDである。聖体礼儀とはカトリックでいうミサ,プロテスタントでいう聖餐式に相当する重要な儀式である。また,聖ヨハネ・クリソストムとは,347年頃生まれ,398年に帝国の首都コンスタンチノープルの総主教になり,407年に没した初期教会の聖人である。その名説教ぶりから「金口ヨハネ」と呼ばれ人々に慕われた。このCDに収められた「聖ヨハネ・クリソストムの聖体礼儀」には,「アンティフォン」と呼ばれる左右の詠隊が交互に掛け合いで歌う形式の歌が多く収められている。カトリックのグレゴリオ聖歌とは全く違う曲調に誰しも気付かれるであろう。東洋的といえばよいのか,日本のご詠歌や,アラブ,トルコのイスラム教のお祈りに通じる要素もある。長く伸ばす低音,ソロのこぶしのきいたヴィブラートなども独特である。不思議なハーモニー,エキゾチックな旋律の魅力に満ちた類のない音楽。演奏しているのは1977年に創設された本場ギリシャ アテネのThe Greek Byzantine Choirで,男声のみのコーラスの水準は非常に高い。このCDは海外の音楽誌で非常に高い評価を受けたが,「西洋音楽」とは明らかに違う音楽のユニークさと,この見事な歌唱であれば当然であろう。録音,ジャケットの教会の写真,青を基調にしたプラケースのデザインも秀逸である。
私は前からギリシャ正教の音楽に興味があった。遠い昔ビザンツ(東ローマ)帝国で栄えた東方教会の音楽とはどのようなものだったのか…。そのギリシャ正教の音楽の魅力をはじめて教えてくれたのがこのCDである。聖体礼儀とはカトリックでいうミサ,プロテスタントでいう聖餐式に相当する重要な儀式である。また,聖ヨハネ・クリソストムとは,347年頃生まれ,398年に帝国の首都コンスタンチノープルの総主教になり,407年に没した初期教会の聖人である。その名説教ぶりから「金口ヨハネ」と呼ばれ人々に慕われた。このCDに収められた「聖ヨハネ・クリソストムの聖体礼儀」には,「アンティフォン」と呼ばれる左右の詠隊が交互に掛け合いで歌う形式の歌が多く収められている。カトリックのグレゴリオ聖歌とは全く違う曲調に誰しも気付かれるであろう。東洋的といえばよいのか,日本のご詠歌や,アラブ,トルコのイスラム教のお祈りに通じる要素もある。長く伸ばす低音,ソロのこぶしのきいたヴィブラートなども独特である。不思議なハーモニー,エキゾチックな旋律の魅力に満ちた類のない音楽。演奏しているのは1977年に創設された本場ギリシャ アテネのThe Greek Byzantine Choirで,男声のみのコーラスの水準は非常に高い。このCDは海外の音楽誌で非常に高い評価を受けたが,「西洋音楽」とは明らかに違う音楽のユニークさと,この見事な歌唱であれば当然であろう。録音,ジャケットの教会の写真,青を基調にしたプラケースのデザインも秀逸である。
参考文献:「ギリシャ正教」 高橋保行 著 (講談社学術文庫)
バッハ:復活祭オラトリオ 他
(PHILIPS 442 119-2)
 大作であるマタイ・ヨハネ両受難曲の陰に隠れがちであるが,バッハはイースター用のすばらしい「復活祭オラトリオ」BWV249を書いている。その明るく楽しい雰囲気は,同じバッハの「管弦楽組曲第3番」を思わせる。まず冒頭第1曲のシンフォニアが,早くも浮き立つような楽しい音楽。全体的に明るい曲が多い中で,第5曲のソプラノ・アリアは,リコーダーのオブリガートをバックにした短調のアリアで,しっとりと聴かせる。第7曲テノールのアリアは,イエスの復活を確信したペテロが,喜びをしみじみと噛み締めているかのよう。第9曲アルトのアリアは,オーボエ・ダモーレのオブリガートがちょっと官能的で非常に美しく,"Saget, saget mir geschwinde"(早く教えてください)と繰り返し歌われる旋律が,マグダラのマリアの嬉しさのあまり待ちきれない心を巧みに表現している。終曲(第11曲)では,トランペットが活躍するフル・オーケストラと合唱が復活の喜びを高らかに歌い上げて,力強く全曲を閉じる。このCDには5月のキリスト昇天祭のために作曲された「昇天祭オラトリオ」BWV11も収められており,第4曲のアルト・アリア,第10曲のソプラノ・アリアが美しい。終曲の輝かしいコラール「神は天に昇られた」も感動的である。この曲でもアリアでの管楽器の美しいオブリガートが耳をひく。レオンハルト指揮による演奏は,テンポ感がよく,リズムの切れ味と跳ねるような弾力感も魅力的である。ソリスト陣,オーケストラ(弦と管のソロがすばらしい),合唱共に見事な出来栄えである。
大作であるマタイ・ヨハネ両受難曲の陰に隠れがちであるが,バッハはイースター用のすばらしい「復活祭オラトリオ」BWV249を書いている。その明るく楽しい雰囲気は,同じバッハの「管弦楽組曲第3番」を思わせる。まず冒頭第1曲のシンフォニアが,早くも浮き立つような楽しい音楽。全体的に明るい曲が多い中で,第5曲のソプラノ・アリアは,リコーダーのオブリガートをバックにした短調のアリアで,しっとりと聴かせる。第7曲テノールのアリアは,イエスの復活を確信したペテロが,喜びをしみじみと噛み締めているかのよう。第9曲アルトのアリアは,オーボエ・ダモーレのオブリガートがちょっと官能的で非常に美しく,"Saget, saget mir geschwinde"(早く教えてください)と繰り返し歌われる旋律が,マグダラのマリアの嬉しさのあまり待ちきれない心を巧みに表現している。終曲(第11曲)では,トランペットが活躍するフル・オーケストラと合唱が復活の喜びを高らかに歌い上げて,力強く全曲を閉じる。このCDには5月のキリスト昇天祭のために作曲された「昇天祭オラトリオ」BWV11も収められており,第4曲のアルト・アリア,第10曲のソプラノ・アリアが美しい。終曲の輝かしいコラール「神は天に昇られた」も感動的である。この曲でもアリアでの管楽器の美しいオブリガートが耳をひく。レオンハルト指揮による演奏は,テンポ感がよく,リズムの切れ味と跳ねるような弾力感も魅力的である。ソリスト陣,オーケストラ(弦と管のソロがすばらしい),合唱共に見事な出来栄えである。
英国教区教会の葬送とキリスト復活のための音楽集(1760-1840)
(HYPERION CDA67020)
 CDの原題は"Vital Spark of Heav'nly Flame"(天国の炎の生命の光)で,これにぴったりと言うべき,ジョージ朝の偉大な詩人・画家であったウィリアム・ブレイク(1757-1827)の有名な絵画"The Ancient Days”がCDのカバーを飾っている。英国国教会の各教区で歌われた賛美歌やクリスマス・キャロルなどは"psalmody"と総称され,多様な音楽スタイルのpsalmodyがジョージ朝の1700〜1850年にかけての約150年間に作られた。これらのpsalmodyは,聖週間,イースター,個人の葬送など様々な目的のために作られたものである。しかし,その多くは残念ながら現在すっかり忘れられてしまっている。このCDには,合唱だけで歌われるシンプルな賛美歌から大規模なオーケストラ伴奏を伴う複雑なアンセムまで,幅広いスタイルのpsalmodyがおおよそ年代順に収録されている。この時代は音楽史的には古典派から初期ロマン派の時代であるから,英国国教会の音楽と言っても,それらの時代様式を反映したものになっている。しかし,psalmodyの作曲者の多くは,地方教会の牧師,オルガニスト,あるいは職人などで,いわゆる「プロ」の作曲家はほとんどいない。だから「素人」作曲家が作った稚拙な音楽ばかりだと思うのは早計で,(HYPERIONの選曲もよいのだろうが)音楽的にも優れた聴いておもしろい曲がたくさんある。私が気に入った曲を以下に。
CDの原題は"Vital Spark of Heav'nly Flame"(天国の炎の生命の光)で,これにぴったりと言うべき,ジョージ朝の偉大な詩人・画家であったウィリアム・ブレイク(1757-1827)の有名な絵画"The Ancient Days”がCDのカバーを飾っている。英国国教会の各教区で歌われた賛美歌やクリスマス・キャロルなどは"psalmody"と総称され,多様な音楽スタイルのpsalmodyがジョージ朝の1700〜1850年にかけての約150年間に作られた。これらのpsalmodyは,聖週間,イースター,個人の葬送など様々な目的のために作られたものである。しかし,その多くは残念ながら現在すっかり忘れられてしまっている。このCDには,合唱だけで歌われるシンプルな賛美歌から大規模なオーケストラ伴奏を伴う複雑なアンセムまで,幅広いスタイルのpsalmodyがおおよそ年代順に収録されている。この時代は音楽史的には古典派から初期ロマン派の時代であるから,英国国教会の音楽と言っても,それらの時代様式を反映したものになっている。しかし,psalmodyの作曲者の多くは,地方教会の牧師,オルガニスト,あるいは職人などで,いわゆる「プロ」の作曲家はほとんどいない。だから「素人」作曲家が作った稚拙な音楽ばかりだと思うのは早計で,(HYPERIONの選曲もよいのだろうが)音楽的にも優れた聴いておもしろい曲がたくさんある。私が気に入った曲を以下に。
まず最初に収められているロンドンのオルガニストThomas Greatorex(1758-1831)による"This is the day the Lord hath made"は合唱のフーガがおもしろい。このCDのタイトルにもなっている"Vital Spark of Heav'nly Flame"は最も有名なpsalmodyの一つで,ランカシャーの織工であったEdward Harwood(1707-1787)の作。ソロのソプラノ,アルト,バスのハーモニーが美しい曲。マンチェスターの教会のオルガニストであったRobert Wainwright(1748-1782)の"The Lord is risen"は,トランペットが活躍する輝かしいイースター・アンセムで,ソプラノ・ソロがすばらしく美しい。チェスターの画家であったRichard Taylor(1758-1827)の"Yes! the Redeemer rose"と"Angels, roll the rock away!"は同様にキリストの復活を祝う明るさに満ちた賛美歌で,とくに後者は軽やかなフルートの響きが美しい。バースのHenry Harington(1727-1816)の手になる"I heard a voice from heaven"は,死者の霊を送るのにふさわしいア・カペラの厳粛な音楽。メソジスト教会の創設者として著名な神学者ジョン・ウェズレーの甥で作曲家のサミュエル・ウェズレー(1766-1837)がヘンデルのイースター・ハイム"Rejoice, the Lord is King"を編曲したものは,シンプルな構成ながら合唱がキリスト復活の喜びを力強く歌い上げるところが感動的。
このCDに収録されている音楽でポピュラーなものは一曲もないが,古典派時代の教会音楽,たとえばモーツァルトのミサ曲やヴェスペレが好きな人なら,楽しく聴ける曲がきっとあるに違いない。
シュッツ:復活祭オラトリオ
(SONY CSCR 8385)
 声楽曲の分野でドイツ・バロックの基礎を築いた大作曲家シュッツ(1585-1672)のオラトリオというと,「クリスマス・オラトリオ」が有名だ。この「復活祭オラトリオ」は,「クリスマス・オラトリオ」のように明るく楽しいというより,峻厳でまじめな音楽だが,負けず劣らず美しい作品である。「クリスマス・オラトリオ」より40年も前の1623年の作品だけに,ルネサンス風の古雅な響きがする。
声楽曲の分野でドイツ・バロックの基礎を築いた大作曲家シュッツ(1585-1672)のオラトリオというと,「クリスマス・オラトリオ」が有名だ。この「復活祭オラトリオ」は,「クリスマス・オラトリオ」のように明るく楽しいというより,峻厳でまじめな音楽だが,負けず劣らず美しい作品である。「クリスマス・オラトリオ」より40年も前の1623年の作品だけに,ルネサンス風の古雅な響きがする。
Russian Orthodox Music(ロシア正教の音楽)
(Gimell CDGIM002)
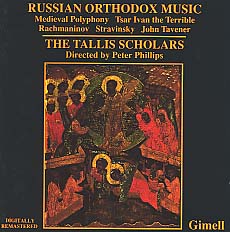 キリスト教の3大宗派カトリック,プロテスタント,正教の中で最もイースターを重要視する宗派は正教である。というより,正教ではイースターが最も大事な(クリスマスよりも)祝祭である。このアルバムは英国屈指の合唱グループであるタリス・スコラーズがロシア正教の音楽を歌ったものである。といっても伝統的な中世の聖歌ばかりではなく,ロシア近現代の巨匠ストラヴィンスキーやラフマニノフの曲も入っており,大変バラエティーに富んだプログラムである。さらに英国音楽ファンには見逃せないのが,ロシア正教に改宗した現代英国の変わり者?作曲家ジョン・タヴナー(1944-)による20分余りの大曲"Great Canon of St. Andrew of Care"。中世的な和声と現代的な和声をミックスしたような不思議としか言いようがない響き。いつものことながら,どの曲でもタリス・スコラーズは一糸乱れぬハーモニーを聴かせる。
キリスト教の3大宗派カトリック,プロテスタント,正教の中で最もイースターを重要視する宗派は正教である。というより,正教ではイースターが最も大事な(クリスマスよりも)祝祭である。このアルバムは英国屈指の合唱グループであるタリス・スコラーズがロシア正教の音楽を歌ったものである。といっても伝統的な中世の聖歌ばかりではなく,ロシア近現代の巨匠ストラヴィンスキーやラフマニノフの曲も入っており,大変バラエティーに富んだプログラムである。さらに英国音楽ファンには見逃せないのが,ロシア正教に改宗した現代英国の変わり者?作曲家ジョン・タヴナー(1944-)による20分余りの大曲"Great Canon of St. Andrew of Care"。中世的な和声と現代的な和声をミックスしたような不思議としか言いようがない響き。いつものことながら,どの曲でもタリス・スコラーズは一糸乱れぬハーモニーを聴かせる。
バッハ:カンタータ第106,4,78番
(POLYDOR F20A 20067)
 第4番「キリストは死の縄目につながれたり」が復活節第1主日用のカンタータであり,バッハの数多くの教会カンタータの中でも屈指の名作。全曲の基調になっているのは,ルター派の復活祭コラールであり,これが次々と変奏されていく。最初から最後までこれだけ緊張感に溢れたカンタータは,バッハのカンタータ多しといえどもそれほど多くはない。6曲目のバス・アリアは全曲の白眉。このCDではフィッシャー=ディースカウが歌っていることもあって,深い感情の表出が感動的である。他に収められている第106番「神の時こそいと良き時」と第78番「イエスよ,汝わが魂を」の2曲も,バッハのカンタータで10指に入る名作。第106番のリコーダーのオブリガードとソロの掛け合いの美しさ,第78番のテノールとバスのアリアの切実さ。カール・リヒターの遺したカンタータ録音の中でも,これら3曲の演奏は傑出している。
第4番「キリストは死の縄目につながれたり」が復活節第1主日用のカンタータであり,バッハの数多くの教会カンタータの中でも屈指の名作。全曲の基調になっているのは,ルター派の復活祭コラールであり,これが次々と変奏されていく。最初から最後までこれだけ緊張感に溢れたカンタータは,バッハのカンタータ多しといえどもそれほど多くはない。6曲目のバス・アリアは全曲の白眉。このCDではフィッシャー=ディースカウが歌っていることもあって,深い感情の表出が感動的である。他に収められている第106番「神の時こそいと良き時」と第78番「イエスよ,汝わが魂を」の2曲も,バッハのカンタータで10指に入る名作。第106番のリコーダーのオブリガードとソロの掛け合いの美しさ,第78番のテノールとバスのアリアの切実さ。カール・リヒターの遺したカンタータ録音の中でも,これら3曲の演奏は傑出している。
バッハ:カンタータ第92,126,23番
(POLYDOR POCA-3012)
 復活節前第7〜9日曜日用のカンタータ3曲を収めたアルバム。これもカール・リヒターの遺したかけがえのないバッハ演奏である。3曲の中では最も大作の第92番「われは神の御胸の思いに」がやはり一番聴き応えがある。オーボエ・ダモーレが美しい冒頭合唱と4曲目のアルト合唱,牧歌的な美しさに満ちた8曲目のソプラノ・アリア。フィッシャー=ディースカウ,ペーター・シュライアー,エディット・マティスと二度とは望めぬ豪華なソリスト陣による歌唱が聴きものである。
復活節前第7〜9日曜日用のカンタータ3曲を収めたアルバム。これもカール・リヒターの遺したかけがえのないバッハ演奏である。3曲の中では最も大作の第92番「われは神の御胸の思いに」がやはり一番聴き応えがある。オーボエ・ダモーレが美しい冒頭合唱と4曲目のアルト合唱,牧歌的な美しさに満ちた8曲目のソプラノ・アリア。フィッシャー=ディースカウ,ペーター・シュライアー,エディット・マティスと二度とは望めぬ豪華なソリスト陣による歌唱が聴きものである。
バッハ:カンタータ第104,12,108番
(POLYDOR POCA-3015)
 復活節後第2〜4日曜日用のカンタータ3曲を収めたアルバム。第104番「イスラエルの牧者よ,耳を傾けたまえ」5曲目のゆったりとした弦の調べに乗った牧歌的なアリアの美しさは,フィッシャー=ディースカウの朗々とした歌いぶりもあって忘れがたい。第12番「泣き,嘆き,憂い,怯え」の2曲目の合唱は,晩年の名作「ロ短調ミサ曲」に転用された曲で,悲痛な響きが胸を打つ。しかし私の一番好きなのは第108番「わが去るは汝らの益なり」である。美しいヴァイオリン・オブリガートでテノールが歌う2曲目のアリアの素晴らしさ。5曲目のアルト・アリアにはバッハらしくない?ロマンティックな魅力がある。
復活節後第2〜4日曜日用のカンタータ3曲を収めたアルバム。第104番「イスラエルの牧者よ,耳を傾けたまえ」5曲目のゆったりとした弦の調べに乗った牧歌的なアリアの美しさは,フィッシャー=ディースカウの朗々とした歌いぶりもあって忘れがたい。第12番「泣き,嘆き,憂い,怯え」の2曲目の合唱は,晩年の名作「ロ短調ミサ曲」に転用された曲で,悲痛な響きが胸を打つ。しかし私の一番好きなのは第108番「わが去るは汝らの益なり」である。美しいヴァイオリン・オブリガートでテノールが歌う2曲目のアリアの素晴らしさ。5曲目のアルト・アリアにはバッハらしくない?ロマンティックな魅力がある。
バッハ:カンタータ第1,182,158番
(POLYDOR POCA-2033)
 CDの最後に収められている第158番「平安なんじにあれ」が復活節火曜日(第3祝日)用のカンタータである。事実上バスの独唱カンタータで,合唱は終曲コラールだけに登場する。全4曲10分ほどの小曲であるが,その半分以上の長さを占める2曲目のアリアが実にすばらしい。美しいソロ・ヴァイオリンのオブリガード(オットー・ビュヒナーの演奏が見事)にのってバスが「世よ,さらば! 我は汝に倦みたり…」を堂々と歌い出し(フィッシャー=ディースカウの歌唱も見事である),さらにソプラノのバック・コーラスが加わる。このすばらしいヴァイオリン・オブリガード付きのアリアを聴いて,同様な「マタイ受難曲」のアリアを連想する人もいるだろう。第1番「輝く曙の明星のいと美しきかな」も見逃すわけにはいかない。バッハの教会カンタータの中でも,合唱コラール,ソロ・アリア共にとりわけ明るく美しいメロディーに満ちた,名誉あるバッハ作品番号1(BWV1)にふさわしい名作である。もう1曲の第182番「天の主よ,汝を迎えまつらん」は全曲で30分以上を要する大作で,ブロックフレーテ・オブリガードが美しいアルトの深々としたアリアが白眉である。この盤でも,カール・リヒターの指揮とソリスト陣のすばらしさは言うまでもない。
CDの最後に収められている第158番「平安なんじにあれ」が復活節火曜日(第3祝日)用のカンタータである。事実上バスの独唱カンタータで,合唱は終曲コラールだけに登場する。全4曲10分ほどの小曲であるが,その半分以上の長さを占める2曲目のアリアが実にすばらしい。美しいソロ・ヴァイオリンのオブリガード(オットー・ビュヒナーの演奏が見事)にのってバスが「世よ,さらば! 我は汝に倦みたり…」を堂々と歌い出し(フィッシャー=ディースカウの歌唱も見事である),さらにソプラノのバック・コーラスが加わる。このすばらしいヴァイオリン・オブリガード付きのアリアを聴いて,同様な「マタイ受難曲」のアリアを連想する人もいるだろう。第1番「輝く曙の明星のいと美しきかな」も見逃すわけにはいかない。バッハの教会カンタータの中でも,合唱コラール,ソロ・アリア共にとりわけ明るく美しいメロディーに満ちた,名誉あるバッハ作品番号1(BWV1)にふさわしい名作である。もう1曲の第182番「天の主よ,汝を迎えまつらん」は全曲で30分以上を要する大作で,ブロックフレーテ・オブリガードが美しいアルトの深々としたアリアが白眉である。この盤でも,カール・リヒターの指揮とソリスト陣のすばらしさは言うまでもない。
A Celebration of Easter (世界のイースター)
ATVC-002 (VHS)
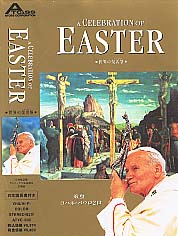 ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の話に加えて世界のイースターの映像や聖歌で構成されたビデオ。とりわけローマのサンピエトロ大聖堂で執り行われる四旬節といわれる40日間や復活祭直前の3日間の行事は,カトリックの典礼を知る上で大変興味深い。一連の行事がクリスマスのミサより厳粛さを感じさせるのは,聖書の中の様々な記述に基づいているからであり,キリスト教の神秘的・秘儀的な側面を感じさせるものでもある。
ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の話に加えて世界のイースターの映像や聖歌で構成されたビデオ。とりわけローマのサンピエトロ大聖堂で執り行われる四旬節といわれる40日間や復活祭直前の3日間の行事は,カトリックの典礼を知る上で大変興味深い。一連の行事がクリスマスのミサより厳粛さを感じさせるのは,聖書の中の様々な記述に基づいているからであり,キリスト教の神秘的・秘儀的な側面を感じさせるものでもある。

