�G�b�Z�C
���E�F�[���Y�̃N���X�}�X
�W�F�[�����}�C�P���E�}�[�X�@���^��ш�q�@��i�a���[�j��1,700
 �@�E�F�[���Y�̌Ós�Z���g�E�f�B���B�b�Y�ł̐S���܂�N���X�}�X�̏�i��`�����G�b�Z�C�B�ڂ����́C�������B
�@�E�F�[���Y�̌Ós�Z���g�E�f�B���B�b�Y�ł̐S���܂�N���X�}�X�̏�i��`�����G�b�Z�C�B�ڂ����́C�������B
���u�Â��ɗ����e���Y��v
�ؑ������@���i���t���Ɂj��350
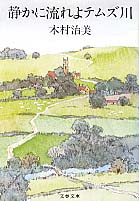
�@���s��܂���܂����u�����̃����h������v�ɑ������҂̉p�������h���E�G�b�Z�C��Q�e�B�Ƃ����Ă��C��������ł�20�N�ȏ�O�ł���B�����C�p���Ƃ��Ƀ����h�����u�l�^�v�ɂ����G�b�Z�C�̐��͐�����Ȃ��قǏo�Ă��邪�C�{���͂��́u�������v�̈�Ƃ����Ă悢�ł��낤�B���Ƃ����Œ��Ҏ��g���u�����퐶���̒�����̕�����]�����邢�́������҂̔�r�����_���Ƃ������ׂ��G�b�Z�C�̃X�^�C�����m�����邱�Ƃ��ł����v�Ǝ������Ă��邪�C���ł͉p���G�b�Z�C�X�g�̑������Ƃ��Ă���X�^�C�����C20�N�O�ɂ͐V�������̂ł������̂��B�{���Œ��҂́C�u�����̃����h������v�ȗ��R�N�Ԃ�i1977�N�j�ɖK�ꂽ�p�������ɑ傫���ς���Ă���̂ɋ����C�����Ɂu�i�v�v�ɕς��Ȃ��ł��낤�p���̎p���ڂɂ���B���Ƃ��Γ����ɂ��ď����ꂽ�G�b�Z�C�Ȃ��20�N�O�̎��ۂŌ���ɂ����Ă͂܂邱�Ƃ́C����߂ď��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ��낪�p���ł́u�i�v�v�ɕς��Ȃ������E�K�������Ƃ��đ��݂��邱�Ƃɉ��߂ċC�Â������̂ł���B�����Ƀ}�[�K���b�g�E�T�b�`���[���܂������������n�߂�O�́i�J���}���t�̎���́j������ԂƂ����Ă悢�u�p���a�v�̏����肰�Ȃ��`����Ă��āC���̎l�����I�̉p���Љ�̑傫�ȕω��������������ɂ͂����Ȃ��B1970�N��C�p���̏��w�Z�ł͘J���}���t�ƕێ�}���t�i�T�b�`���[)����ւ��邽�тɖ����������o����p�~���ꂽ�肵�������ł���B�����̑��q���o�[�X�̏��w�Z�ɒʂ��Ă����Ƃ��C�X�N�[���E�f�B�i�[�i���H�j�͗L�������ǁC�����̓^�_�ł����Ȃ��Ǝv�������Ƃ����������C�����P�{�ɂ��������W���Ă������Ƃ�m�苻���[�������B
���u�C�M���X���ۍl�v
�ؑ������@���i���t���Ɂj��419

�@�ؑ��������̉p���G�b�Z�C�����Ō�20�N���o�߂��Ă����͓I�Ȃ̂́C�p���Ɠ��{�̊Ԃɉ���������I�ȑ�����������ʂ̓��{�l�̖ڂłƂ炦���u���Ր��v�����邩�炾�낤�B���p�̈Ⴂ���w�E���邱�Ƃ͒N�ɂł��ł��Ă��C���̔w��ɂ�����j�E�����E�Љ�I�w�i���l���邱�Ƃ͓���B����҂͏_�炩�����͂ł��肰�Ȃ������Ă����̂��B�{���́u�C�M���X���ۍl�v�C�u���{�l�ƊO���l�v�C�u�C�M���X���H�������v�̂R������Ȃ邪�C���j�ƕ��w�̘b�肪�L�x�ȁu�C�M���X���H�������v�����ɂ͂��������납�����B
���u����C��n��v
�[�c�S��@���i���t���Ɂj��427

�@�����̓��{�l�������l�Ɗւ��Ȃ���d�������C�N�������ʂɃ��[���b�p���s���y���ލ��ł͑z�����ɂ������Ƃ����C��̑O�i�Ƃ����Ă���O���獂�x�������ɂ����Ă̎���̂��Ƃł��邪�j�ɂ́C�����o��ŊC��n��C�������E�֔�э����ۉ��́u�p�C�I�j�A�v�Ƃ������ׂ����{�l�����������B�{���͂����������{�l�Ƃ��āC���ې��X�`�����[�f�X�C�h�C�c�ɏo���������i�E�l�C���[���i�h�C�c�j�h���Y�z�v������グ�C�ށi�ޏ��j��̐������E�̌��������Ȃ���̂ł���������Ԃ����m���E�t�B�N�V�����ł���B
�@�U�̘b�����钆�ŁC�u�I�[�y�A����v�Ƃ����b���p�����w�̐̂�m���ŋ����[���B���ł͊��S�Ɏ���ƂȂ��Ă���u�I�[�y�A�iAU PAIR�j�Ƃ́C�p���̉ƂŏZ�ݍ��݂œ����C�ߑO���͉Ǝ�����`������C�q�ǂ��̐��b�����C�ߌ�͏T�ɉ��߂��̌�w�w�Z�ɒʂ��ĉp�������鏗���̂��Ƃ��w���B�u�I�[�y�A�E�K�[���v�̐��x�́C���w����قnjo�ϓI�ɗ]�T�̂Ȃ����{�̏������p��̕��̂��߉p���ɑ؍݂��邽�߂֖̕@�ŁC�����̉p���͂���`���̋��l��Ƃ������Ƃ������āC���ʂɃI�[�y�A�p�̃r�U�����Ċ��}���Ă����炵���B�I�[�y�A�̈����Ǝ҂����������Ƃ������Ƃ��B1970�N��ɂ͓��{�l�̃I�[�y�A�E�K�[���������������h���ɑ؍݂��Ă����炵���C���������h���ɒ��݂��Ă������҂����ۂ̘b���������������Ă����悤���B���̓��{�l�I�[�y�A���x��1980�N���ɔp�~����C�r�U����������Ȃ����ƂɂȂ����B��������łɉ����ߋ��̂��ƂƂȂ�C���ł͌o�ϓI�ɗ]�T�̂�����{�l�����������������h���𒆐S�Ƃ�����w�w�Z���w���Ă���̂͂����m�̒ʂ�B
�@���͖{����ǂނ܂ŃI�[�y�A���x�Ȃ���̂��ߋ��ɉp���ɑ��݂������Ƃ���m��Ȃ��������C�����̃I�[�y�A�E�K�[���̑̌��k�ɂ́C���ǂ�ł��Ȃ�قǂƎv�킹��Ƃ��낪����B�^�Ԃ̂ɋ�J����قǏd���čl�����Ȃ��悤�Ȗҗ�ȉ��𗧂Ă�t�[�o�[�̑|���@�C�q�ǂ��ɂ́u�����v�Ȕӂ��т�^���Ȃ��K���Ȃǂ́C���ł����Ă͂܂邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�悭������Ȃ��̂́C�u�C�M���X�̃\�[�Z�[�W�͓��{�ł݂͂��Ȃ�����Ȑ��i�Ȃ̂ŁC�悭�Ă��Ȃ��Ɓu�Łv���c��̂ɁC�I�[�y�A�E�K�[���̏Ă���������Ȃ��Ƃ����ĉp���l�Ɏ�����v�Ƃ����b�ł���B����́C��̂ӂɂ�ӂɂ�\�[�Z�[�W�̂��Ƃ������Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ����C�u�Łv�Ƃ͂Ȃ낤�H�P�ɐ��̃u�^���͂悭�Ȃ��Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ�̂��낤���c�B
���u�[��Y �t���L�v
�[��Y�@���i�����V���Ёj��369

�@1929�N�ɐ��܂�C1973�N2������1975�N11���܂ŁC���@����܂Œ����V���̊Ŕu�V���l��v�����M�������҂́C�}�������a�̂��߂��̂܂܋A��ʐl�ƂȂ����B���҂́u�V���l��v�i�����V���Ђ̕��ɂŏo�Ă���j�́C�Љ�ɑ���s���D�����܂Ȃ����ƁC�i���̍������͂����Ȃ��ǂ�ł�����łB�{���ɂ́C�V���Ђ̌�w���K���Ƃ���30�˂̂Ƃ��Ƀ����h���ɗ��w�����Ƃ��̓��L�Ȃǂ��L����Ă���B������40�N�ȏ���O�̂��Ƃł��邩��C������̃����h���Ƃ͑傫���Ⴄ�ł��낤���C�p���l�̋C�����̂��͍̂����̂��ς���Ă��Ȃ��B���P�C�ȁE���̏��荇���Ƃ��������_�͎��̉p���؍ݒ��ɂ����������Ƃ��B�u�����Ƃ́C�匚�z�⍋�Ȏ����Ԃł͂Ȃ��C�܂�C�Ă���̍����ł͂Ȃ��C���O�̒��ɂ��ݍ���ł���l�ԓI�Ȋ���C�s���̍L���C�[���ł͂Ȃ����B�v�Ƃ������҂̌��t�قǁC�p���Ƃ������̕����������\���Ƃ��ɓK�Ȍ��t�͂Ȃ��悤�Ɏv����B�D�ꂽ�L�҂ɂ��ăG�b�Z�C�X�g�̒��҂����̉p����������ǂ̂悤�ɏ������낤�B
���u����̂܂ق������v
������������@���i�V�����Ɂj��476
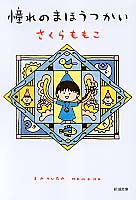
�@���͎��́u���т܂�q�����v�̃t�@���ŁC�n�[�h�J�o�[�̈����Łu���т܂�q�����v��C2000�N�ɏo�ł��ꂽ��Ҏ��g�ҏW�̎G���u�x�m�R�v�������Ă��邵�C���T���j���ɕ��f����Ă���e���r�A�j�������j�ƈꏏ�Ɍ��Ă���B�Ƃ��낪�C�����Ȃ��ƂɁC��҂ł��邳�������������Ɖp���Ƃ̈ӊO�ȊW�ɂ́C���܂őS���C�����Ȃ������B�{���̃^�C�g���ł���u����̂܂ق������v�Ƃ́C�����h���ɍݏZ���C���X�̗����̏o��悤�ȊG�{���₵��47�̎Ⴓ�Ő������G�{��ƃG�E���[���E���E�J�C���̂��Ƃł���B�����炳��͍�2�̓~�ɔނ̊G�{�Əo��C���̂��炵���A�[�e�B�X�e�B�b�N�ȊG�Ɉ�ڍ��ꂵ�Ă��܂����B����ȗ��C�J�C���ւ̎v���͂����ƕς�邱�ƂȂ��ޏ��̐S���߂Ă����悤���B�ł����ƂȂ��ẮC�p���ɍs���Ă�����̐l�ɉ���Ƃ͂ł��Ȃ��B�������c�Ɣޏ��͎v�������B����̐l�̒n��K�ˁC���E�J�C���ƈꏏ�Ɏd���������l�̘b�������ƁB
�@�������āC�������������s�͏t�̉p���ւƓn��C�ޏ�����D���ȃE�F�b�W�E�b�h�̖{���n�X�g�[�N�E�I���E�g�����g�ł̍H�ꌩ�w����ɁC���O�̃��E�J�C�����悭�m��l�����������h���ɖK�˂�B���������K�₵���p���l�̉Ƃŋ����肵�C��ыN�����r�[�ɐQ�ڂ��ē��َq��v�����C�U�X���ݐH��������܂�����C�I�V�b�R���������Ȃ��āc�Ƃ����C���҂̕��g�ł��邿�т܂�q������f�i�Ƃ����鎸�s�k�ɂ͎v�킸���Ă��܂��B����ōD��S�̋������҂̂��ƁC��ނ̍��ԂɃ����h���ɂ���G�i�����l�`�̓X��C�������ȍ����������`�����Ƃ��Y��Ȃ��B�S�҂�ʂ��āC���[�����X�ȕM�v�̒��ɂ��C���҂̊ώ@��⊴�z�͂������ɉs���B����ɁC���E�J�C���̔������G�ƁC���҂̃��E�J�C���ւ̃I�}�[�W���Ƃ������i�������Ղ�ƃJ���[�Ŏ��^����Ă��āC�����߂Ă��邾���ł��K���ȋC���i���т܂�q�����̃Z���t�݂������Ȃ��j�ɂȂ�B
�@���ɉ��ɍۂ��āC���ʃC���^�r���[�u�G�ɂ��Ă̎v���o�v�������Ɏ��^����Ă���C�������t�@���ɂ͔ޏ��̎��`�I��z�Ƃ������ׂ���Ό������Ȃ����e�ł���B���E�J�C���̒���ژ^���f�ڂ���Ă���̂��ނ̃t�@���ɂ͊������B������_�C���҂炵����ʁu�C�M���X�̐H�ׂ��̂͑S�̓I�ɂ��������Ȃ��̂ŁC�C���h����������H�ׂ�Ɍ���v�Ƃ����ނ̃X�e���I�E�^�C�v�I�Ȍ��������J��Ԃ��o�Ă���̂͂�����Ǝc�O�B
���u�G�{������ā@�����̂��݂ցv
�]�����D�@���i�V�����Ɂj��667

�@���͍]�����D�̏������P�����ǂ��Ƃ��Ȃ��̂ŁC���̐l�C������Ƃɂ��Ę_���鎑�i�͑S���Ȃ��̂����C���̊G�{�G�b�Z�C�i�S35�ҁj�Ŏ��グ��ꂽ��i�̃��C���A�b�v�ƁC�����̊G�{�ɑ���I�m�E��̓I�ł��������j�[�N�ȕ]��ǂނƁC���̐l�̕��X�Ȃ�ʊ��ƕ��͗͂̕З�����������B�p���̊G�{�ł́C�A���\���E�A�g���[����́u�G�{�@�O���C�E���r�b�g�̂��͂Ȃ��v�C�E�B���A���E�j�R���\���́u���������r���v�C�r�A�g���N�X�E�|�^�[�́u�s�[�^�[�E���r�b�g�̊G�{�V���[�Y�v�ȂǁC�Â��G�{�����グ���Ă���B����p���̊G�{��Ƃ����グ���Ă��Ȃ��̂�������Ǝc�O�����C���̍��ɂ����炵���G�{��Ƃ���������̂Œv�����̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B�ǂ̃G�b�Z�C�ł����ۂ̊G�{�̔������J���[�ʐ^���ڂ��Ă��āC���̖{��ǎ҂����ɃC���[�W���Ȃ���G�b�Z�C���y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B����ł��܂ǂ�667�~�Ƃ́C����قǔ����ē������C���ɂȂ������ɖ{�͍ŋ߂Ȃ��B�G�{�t�@���K���I
���u�q��ăm�[�g�v
�с@�]�E��������@���i���ԏ��X�j��1,300
�@�D�������͕�����邯��ǂ��p���u�[���̗����҂̈�l�ɈႢ�͂Ȃ��с@�]����TV�ł����Ȃ��݂̏����ٌ�m�������䎁���u�q��āv�ɂ��đ����Ɍ�荇�����Βk�W�B�{�����p���{�ɓ����ׂ����ǂ������������C�ю����p�����w���̎q��đ̌��������ɏo�Ă���̂Ŏ��グ���B�u�C�M���X�ɉƑ��ő؍݂�����N�Ԃ����q�̖�������v�Ƃ�����������C�c�Ƃ��Ƒ��D��Ƃ����p���Љ���炱���̘b�ł��邪�C�䂪�Ƃ̏ꍇ�������������Ȃƍ��ɂ��Ďv����B��l�̑Βk�ɔ[���ł���Ƃ���C����͂ǂ����ȂƎv����Ƃ���F�X���邪�C���珑�ɂ��肪���Ȗ��ɋ��P�L���Ƃ��낪�Ȃ��̂������B
���u�q�������̃����h���v
�~�{�n���@���i���X�j��1,900

�@�@�{���́C��w�̉p���w�̐搶�ł��钘�҂��Ƒ���A��ă����h���ɗ��w�����Ƃ��̌o�����C��l�̗c�����q�q�f�ƃ��E�̏��w�Z�����𒆐S�ɒԂ����G�b�Z�C�ł���B�u��l�v�̃����h���؍L�͑|���Ď̂Ă�قǂ��邯��ǂ��C�u�q�ǂ��v�̎��_�ɗ����������h���؍L�͂���قǑ����Ȃ��B���̓_�ʼn��l�̂���{�ƌ����邾�낤�B�S���łT�͂���Ȃ邪�C��Ԃ̓ǂݕ��͂�͂�u�C�M���X�̏��w�Z�v�ł���B�q�ǂ��������h���̏��w�Z�Ŏ��ۂɌo���������Ƃ����ɂȂ��Ă���̂ŁC�b����̓I�ŕ�����₷���B�w�Z�ɂ���ċ�����j������傫���Ⴄ���C�����h���ƒn���ł͋�������܂��Ⴄ�ł��낤����C�����̗Ⴞ���ňꗥ�Ɂu�p���̏��w�Z�Ƃ͂��������Ƃ��낾�v�Ƃ͌����ɂ�������ǂ��C�q�ǂ���A��ĉp���ɑ؍݂���l��C���p�̏�������̈Ⴂ��m�肽���l�ɂƂ��ĎQ�l�ɂȂ�{�Ƃ����邾�낤�B
���u�Â��ĖL���ȃC�M���X�̉� �֗��ŕn�������{�̉Ɓv
��`�c�q�@���i��a���[�j��1,600

�@��`�������̒���u�����C�M���X�ɕ�炷�킽���v�́C�����~�[�n�[�ȃG�b�Z�C�Ƃ������������Ă�����D���ɂȂ�Ȃ��������C���̖{�͂����B���̖{�Œ��҂������������Ƃ͒����薼�������ʂ�Ȃ̂����C���̖{�����e�I�ɂ����ƓI�ɂ������������R�����͎��̂悤�Ɍ���B���Ȃ킿�C��`���͓��{�l�̉p���ɑ���l�X�ȓ����v������̑Ώۂ̒�����C���̒��ł����{�ł͍ł���������ȁi���ꂾ���ɓ��{�l�̓���͂Ƃ��ɋ����j�u�p���I�ȕ�炵�v�̊�b�ƂȂ��Ă���u�Ɓv�ɑ�ނ��i���ē��p�̉ƁE��炵�̈Ⴂ����̓I�ɔ�r���Ă���B�p���̕��w�≹�y�͓��{�ł��y���߂�B�p���̗����₨�َq�����{�Ŗ��키���Ƃ��ł���B�g���Ȃ�ŋ߂͂ނ�����{�̕����������̂���ɓ��邭�炢���B�������C�p���l���Z��ł���悤�ȉƂɏZ�݁C�p���l�̂悤�ȕ�炵�������邱�Ƃ́C���{�ł͂܂��s�\�ł���B�����āC����͂����̂���Ȃ��Ƃ������o�ϓI�Ȗ�肾���ł͕Еt����ꂸ�i�Ƃ̉��i�������炢���Γ��{�̉Ƃ̕�����قǍ����Ƃ������ƂɂȂ낤�j�C�̂��猻�݂Ɏ�����p�̒������j�C�`���C�v�z�̍����W���Ă��邾���ɂ���������B�ł����{�I�Ȗ��́C���{�̉Ƃ͉p���̉Ƃƈ���āu���Օi�v�ł���Ƃ����_�ł��낤�B�Â��Ȃ�Δ���������ԂƓ������o�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�p���l�ɂƂ��ẮC�ƂƂ͎����ƈ�g���́C���X�g�����肪����������C�Â��Ȃ����肵������Ƃ����Č��̂Ă邱�ƂȂǂƂ�ł��Ȃ����ƂȂ̂ł���B�p���l�ʼnƂ̉�������Ƃ����l�������̂��C�Ƃɑ��鈤��̌���ꂾ�낤�B���Ҏ��g�͓����s���ɉp�����̃R�e�[�W�����Ă��炵�����C�唼�̐l�ɂƂ��Ă͋��ނׂ����Ȃ����ƁB���̈Ӗ��Ŗ{���͎����s�\�Ȗ���Ԃ������́u���[�g�s�A�v�{�Ȃ̂ł���B
���u���m���ێn���v
�[�c�S��@���i���Y�t�H�j��900
�@���{�q��̍L�����ł��������҂��C1976�N�Ƃ���������25�N���O�ɏo�����G�b�Z�C�W���Ȃ���������グ��̂��H����́C���̖{�̒��́u�}�[�N�X�E�A���h�E�X�y���T�[�]�v�Ƃ����G�b�Z�C���C���p�̏�����̍��ق�I�m�ɑ����Ă��āC21���I�ɂȂ������ǂ�ł��������낢����ł���B���҂̗F�l�ł������W���[�i���X�g�̃`���[���Y����Ƃ��̉����C���{�̃f�p�[�g��X�[�p�[�Ŕ����������ē��{���i���g�������ɁC�����ɂ����ɂȂ��Ă��܂��u�ϋv���v�̒Ⴂ�q�ǂ��̉�����C�V�[�Y�����ƂɁu�f�U�C���v�����낱��ƕς��ǎ���f�B�i�[�Z�b�g�ɂ������茙�C�������Ă��܂����Ƃ����B���̂��Ƃ҂��ނ̉�����ɘb�����Ƃ���C�؉p�o���̒���������́u�����I�v�Ƃ�������ŁC�u���Ȃ��Ɂi�����h���o���Łj�q���̃p���c�����Ă��Ă���C�Ȃ�ė��ނ̂͂Ƃ��Ă��c�����Ǝv���Ėق��Ă����ǁC�ǂ����i�`���[���Y����ɗ��܂�āj�����Ȃ炤���̎q���̂���C�O�N�������Ă��Ă�B�v�ƌ�����n���B�����Ē��҂́u�낭�ɏ��ނ������Ă��Ȃ��A�^�b�V���E�P�[�X���d�X�����Ԃ牺���āC�����h����`�ɍ~�藧�������́C���p�����̌Ï��[����������������������Ў�ɁC���q��v�w�A��̑����X�[�p�[�}�[�P�b�g�C���{�ł����ΐ��F�C�������邢�̓_�C�G�[�ɂ�����C�}�[�N�X�E�A���h�E�X�y���T�[�̔����������炱����ƁC���낤��߂�������n���ɂȂ�����ł��B�v�B
�@���̏���悤�ŏ��Ȃ��b�����l�����I��ɉp���ɑ؍݂������̊����ł́C���̓��{�Ŕ����Ă���q���̉����́u�ϋv���v���p���̂��̂��Ƃ��ɗ���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B25�N�̊Ԃɓ��{���u�i���v�����̂ł͂Ȃ����H�������C�}�[�N�X�E�A���h�E�X�y���T�[�̉����i�����łȂ��ߗ��i�S�ʁj�������Ńf�U�C�����I�[�\�h�b�N�X�ŁC�������ϋv���ɗD��Ă���Ƃ����͖̂{���ł���B�p���Ń��Z�v�V�����E�N���X�i���w�Z�P�N���j���������j�̉p���l�̓������̂����C���Ȃ�̐��̐��k�����Ă��鐧���͖��炩�ɂ��Z�����₨�o�����̂������肾�����B�V�����̉䂪�q�Ɂu�s�b�J�s�b�J�̐����v�𒅂��Ă�낤�Ƃ������o�͉p���̐e�ɂ͂��܂�Ȃ��悤���B�����炱�����҂������悤�ɁC�u�p���ł͏㒅�����łȂ������ł��Z�����ւƂ������肪�p����Ă����v�̂ł��낤�B���{�̎Љ�K���ł͂Ȃ��Ȃ�������낤���ǁC21���I�̒n�������l����ƌ��K��Ȃ�������Ȃ����Ƃ̂ЂƂł��낤�B
���u�C�M���X�͂��������v
�с@�]�@���i���Y�t�H�i���Ɂj�j��466
�@���킸�ƒm�ꂽ�����́u�p���u�[���v�̐�ڂ������L�O��I�x�X�g�Z���[�E�G�b�Z�C�B���ɔłł́C���߂ɏo�����}�Њ��̒P�s�{�Ƃ́u���V�s�v���ς���Ă���B���ɂ���ȉƃt�@�[�K�\���́u���[�X�g�`�L���v���������납�����B
���u�C�M���X�͖������v
�с@�]�@���i���Y�t�H�i���Ɂj�j��448
�@�u�C�M���X�͂��������v�̎o���҂����C���ɂ͂�����̕����������낢�B��P�b���X�k�[�J�[�̘b���o�Ă��邪�C�����{�E�搶���u�Ⴂ���j�q�v�̃`�����s�I���Ƃ��Ă����Ă����X�e�B�[�u�E�f�C���B�X�̎���͊��ɉ�������C�����؉p���݂͂��߂ȕ����������Ă��邱�Ƃ����������B��P�O�b�́u�Â��N���X�}�X�@�h���N���X�}�X�v�͕M�̂��܂��������ď킹��B���N���ONHK�̉q�������ŁC�����{�E�搶���p���̉ƒ�ŃN���X�}�X�E�v�f�B���O��H�ׂ�Ƃ������̐��ԑg���������B�����Ƃ��̂Ƃ����搶���S�́u�d���Ƃ͂�������Ȃ��̂�H�ׂ�̂͂��₾�Ȃ��B�v�Ǝv���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�S�҂ɂ킽���č�Ƃ̃{�X�g���v�l�̎v���o���Ԃ��Ă���B���̃G�b�Z�C�ɐG������Ď�ɂ����{�X�g���v�l�̃O���[���E�m�E�E�V���[�Y�i�]�_�ЂŖM��j�́C�Â��悫����̉p��������������z���͂ɂ��ӂꂽ�t�@���^�W�[�������B
���u�����{�E�搶�@�C�M���X�A��v
�с@�]�@���i���Y�t�H�i���Ɂj�j��438
�@���̃G�b�Z�C�́C��̂Q���Ƃ͂��Ȃ�قȂ�C�u�����̂ɂ���������v�Ƃ������C�p���ł̎��ۂ̐����Ń����{�E�搶���C�Â������Ȃ�ׁX�Ƃ������Ƃ��b��̒��S�ƂȂ��Ă���B��������̂́C�܂��p���ɂ�����Ԃ̃i���o�[�́i���{�Ƃ͂܂�ňႤ�j���R�Ƃ����t�����B���Ƀ����{�E�搶���l���B���傢�Ɋ��S�����p���̏��w�Z�́u�����I�E�V�X�e�}�e�B�b�N�ŁC�������b���������낢�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̉p�ꋳ���v�B���{�ł��܂�ʉp��̍��Y���ȏ��Ȃǎg���̂���߁C�S������ɐ�ւ�����ǂ�Ȃɂ������Ƃ��낤�B
���u�C�M���X�ώ@���T�i�呝��E�V�ҏS�j�v
�с@�]�@���i���}�Ёj��757

�@�ꍀ�ڂ��������������Ă����y�[�W�Ƃ����V���[�g�G�b�Z�C�W�B�ǂ�����ł��C�y�ɓǂ߂�B��͂��ԓ��������̂́C�u���w�Z�v�Ƃ������ڂŁC�u�c���̐��R�Ƃ����p�ꋳ��̃V�X�e���́C�I�b�N�X�t�H�[�h��w�������`���ƌ����Ɋ�Â��č��グ�������ŁC�������č�������D�ꎮ�ɂł������������̂ł͂Ȃ��B���͑��q�►�ƁC���̌�w���ނ��ꏏ�Ɋw�тȂ���C���̖����ȖړI�ӎ��ƍ����I���@�ɁC�r�������������c�v�Əq�ׂ��Ă��邭����ł���B�܂��C�����{�E�搶��^�̃G���_�[�t�����[�E�V�����y���́C�Z�k�t��Waitrose�łP�N����ɓ���B�m���ɍ���̂悢���ݕ����B���{�ł͌������Ƃ��Ȃ��B
���u�z�����w�b�h�̓�v
�с@�]�@���i���Y�t�H�i���Ɂj�j��457
�@���̖{�Ɏ��߂��Ă���G�b�Z�C�͂��ׂĂ��p���Ɋ֘A���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��B�������C���̘b�����肫����ł͂Ȃ��C�������낢�Ƃ����_�ł́C�����{�E�搶�̃G�b�Z�C�����Ƃ����ǂ�����̕��ނɓ���̂ł͂Ȃ����B
���u�C�M���X���v
�с@�]�@���i�u�k��+�����Ɂj��580
�@�����{�E�搶���͂��߂Ƃ���P�O�l�̃C�M���X�т������p���̑��l�ȑ��ʂɃX�|�b�g�ĂČ�����G�b�Z�C�W�B�V���[���b�N�E�z�[���Y�E�t�@���Ƃ��ẮC�͑����v���́u�V���[���b�L�A���̎���͈́v���ʔ��������B
���u�C�M���X�l�G��@�t�E�āv
�o���ەv�@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��660
�@���̖{�́C10�N�ȏ�O���Ȃ�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ����͂��́C�o�����̑�\�I�ȃG�b�Z�C�ł���C���q����H�̔������C���X�g�Ƌ��ɁC���₪��ɂ��u�f���炵���p���v�̃C���[�W������ł����Ɛ���グ��B������Ɣ�����ۂ��Ȃ��Ă��܂������C�p���̃J���g���[�T�C�h�╶����������C�����͎��������ł���B�{�œǂނ����łȂ��C���グ���Ă���b��̈�ł������Łu�̌��v����ƁC�o�����̈ӌ��Ɏ^����������Ƃ��������X�������Ȃ�Ƃ�����o�Ă���͂������C����ł������������G�b�Z�C��ǂފy�����������Ƃ������̂��B�u�P���g�̖��̍��s���~�j��ԁv�������j�[�S���̂��Ƃł���B���ꂪ�{���Ɋy�����u���̍��~�j��ԁv�Ȃ͎̂������۔��������܂��I
���u�C�M���X�l�G��@�H�E�~�v
�o���ەv�@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��648
�@��L�u�t�E�ĕҁv�̑��ҁB���������{���I�ɃC�M���X�́u�t�E�āv�̕����u�H�E�~�v�����C�������������Ƃ��Ă���͎̂d�����Ȃ��B�N���X�}�X���Ȃ�������C�Â������p���̓~�ɟT�ɂȂ�Ȃ������s�v�c���B�Q���͉����y�������Ƃ��Ȃ����C�C���t���G���U�ɂȂ��Ă���҂͖���Ȃ��Ȃ��o���Ă���Ȃ����B�o�������u�t�E�āv���y�����b���������̂ɋ�J���Ă���B�����h���̃Z�[����C�u�����h�C�S�ݓX�Ƃ��������}�Șb��ł��Ȃ�̃y�[�W�������Ă���B�d���Ȃ����B
���u�p������̂܂܁v
�с@�M��@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��629
�@�с@�M�ᎁ�́C�����͓����ł��C�����{�E�搶��}�[�N�X���q��������������ɔᔻ����u�����j�I���W���b�N�h�v�̓��ځB�����h���ݏZ�������C�p����p���l�̈����Ƃ�����Ԃ��Ɍ��Ă������ɂƂ��ẮC�����́u�p���̂��̂Ȃ牽�ł��悵�v�Ƃ��镗���ɂ͉䖝�Ȃ�Ȃ��̂��낤�B�����ɂ͎Љ�h���C�^�[�Ƃ��Ẵv���C�h��������B
���u�p����Z��b�v
�с@�M��@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��648
�@��Ɠ������҂̑��ҁB�b��͂���߂ĎЉ�I�ł���C�u�p�����}���I�s�v�Ƃ������ނ̃G�b�Z�C�Ƃ͍ł������Ƃ���ɂ���B�����{�E�搶��o���ەv���ɂ͔ނ�̘b��E������������C�с@�M�ᎁ�ɂ����̘b��E������������B�ǂ���̃G�b�Z�C���悢���Ƃ������ƂɂȂ�C�ǂސl�̍D�݂ɂ��Ƃ��������悤���Ȃ��B�����C���Ƃ��Ă͉p���ɉi�Z����Ȃ�ʂ����C���������P�N�̑؍݂Ȃ�C�ł��邾���p���̔������Ƃ�������C�f���炵���Ƃ����m���ē��{�ɋA�肽���Ǝv���B�䖝�Ȃ�Ȃ����ȂƂ���͂ǂ̍��ɂ�����̂�����B
���u�p����̐V���v
����q�@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��667
�@����q�����������̉p���̗g�h�Ƃ͑ɂ̂Ƃ���ɂ���B���̃G�b�Z�C�ɂ́C���g��E�{���ʼnp���l�ƕt���������Ƃ��������h���ݏZ�̓��{�l�����A�[�e�B�X�g���ǂ̂悤�Ȍ��Ȏv�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ������Ƃ��C����̏o�����ɑ����ĂԂ��ɒԂ��Ă���B�����Ċy�����C���ɂȂ�G�b�Z�C�ł͂Ȃ��̂ŔO�̂��߁B
���u�C�M���X�l�͂��������v
�����c�q�@���i���Y�t�H�j��1,429
�@�u���{�l�n�E�X�L�[�p�[�������K���Љ�̑f��v�Ƃ������肪���Ă��邱�Ƃ�����C���̖{���ڎw���Ă�����̂������{�E�搶��o�����Ƃ͑ɓI�ł��邱�Ƃ��z������邾�낤�B�Ƃ������C���҂��y�U�Ř_���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B��҂̉p���̗g�h�G�b�Z�C�X�g�́C�p���̘J���ҊK�����Ř_���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��i�Ƃ�����肻�������t�����������X�Ȃ��̂��낤�j�B�J���ҊK���̎��_�ɗ����C�p���Љ�̊K�����ƍ��ʂ𐳖ʂ���ᔻ����{�͐����Ȃ������ɁC���ɐV�N�ł���B����ɂ��Ă��C���҂��ڂ̓G�ɂ��Ă����M���E�����̍L��ȗ̒n���݂ȁC���̓��{�̂悤�Ɂu�_�n����v����āC��@������ꂽ��C�p���̖��͂��������Ă��܂��i���ɊO���l�ɂ́j���낤���C�p���l�^�ʼn҂��ł���o�ŎЂ�NHK��BS������ł��傤�ˁB
���u�C�M���X�l�͂��Ȃ����v
�����c�q�@���i�W�]�Ёj��1,429
�@�����h���Ńv���̃n�E�X�L�[�p�[�Ƃ��Ĉ�l��炷�������̑�Q�G�b�Z�C�B�u���{�ɂ�����{�l�́c�Ȃ����p�����Ύ�����B�������C�p���l�ɂƂ��ē��{�l�́C�o�ς���������C�����̗L�F�l��Ȃ̂��B�c���{�ɂ�����{�l�����������p���ɛZ�т�̂������Ђ˂�B�v�Ƃ����ꕶ�ɂ͍l����������B���͉p�����Ύ����悤�Ƃ͎v��Ȃ����C���Ȃ��Ƃ��������Ƒ�����N��Bath�ɑ؍݂����Ƃ��Ɍ𗬂��������l�B���F���{�l���y�̂��Ă���p���l���Ƃ͌����Ďv��Ȃ��B����Ƃ��C�T�N�C�P�O�N�Ɖp���ɕ�炵�Ă���ƁC�唼�̓��{�l���������̂悤�ȍl����������悤�ɂȂ�̂ł��낤���B
���uꡂ��Ȃ�P���u���b�W�@�ꐔ�w�҂̃C�M���X�v
�������F�@���i�V�����Ɂj��438
�@���҂͐��w�҂ɂ��āC��Ƃ̐V�c���Y�Ɠ����Ă��̑��q�Ƃ����T���u���b�h�B���̒��҂��Ƒ��Ƌ��ɃP���u���b�W�ɑ؍݂������̃G�s�\�[�h��Ԃ����G�b�Z�C�ł���B���������e����Ƃ����ɁC�ǂݎ���Ō�܂ŖO�������Ȃ��b��̓W�J������͂̂��镶�͂͌����B�C�M���X�ɑ���X�^���X������߂āu���������v�Ƃ������C�P�Ȃ�x�^�_�ߑ؍L�ɏI����Ă��Ȃ��̂������B����������ȃC�M���X�؍L�������Ă݂������̂��Ȃ��B
���u�C�M���X�l�̂܂����ȃz���g�v
A.�}�C�I�[���ED.�~���X�e�b�h�@���^�ʖ@���@��i�}�N�~�����@�����Q�[�W�n�E�X�j��980

�@���̖{�̓��e���E�\���z���g������Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悢�B�����z���g�̂��Ƃ����邾�낤���C�������֒����ď����Ă��邱�Ƃ��������낤�B�ǂ���ɂ��Ă��C���[�����X�ȕM�v�Ɠ��e�ŋC�y�ɓǂ߂ď���{���B
���u�C�M���X�l�̕\�Ɨ��v
�R�c�@���@���i���{�����o�ŋ���j��920
�@���̖{�̃^�C�g�����܂�������������B�u�a�m�̍��v�C�u��l�̍��v�C�u�t�F�A�v���C�̍��v�̗����E���ʂɂЂ��ދU�P���𖾂炩�ɂ���Ƃ����ړI�ŏ����ꂽ�{�ł͂��邪�C���҂͓O��I�ɗ��j�I�E���ؓI�ȗ��Â��܂�����ōl�@���Ă���̂ŁC�P�Ȃ�C�M���X�̈����E���ɂ͏I����Ă��Ȃ��B�ނ���C�p���ɂ͂��������U�P�I�ȂƂ��낪���������炱�������̖��͂���p�����`�����ꂽ�Ƃ��钘�҂̈ӌ��ɔ[���B
���u�c���ƃC�M���X�l �|�_���n�肵�V�n�Ł|�v
���я͕v�@���i���{�����o�ŋ���j��830
�@�C�M���X�l�͂Ȃ��c���ɂ������̂��H���̗��R�҂́C�����h���x�O�̓c���s�s�C�X�R�b�g�����h�̃n�C�����h�C�E�F�C���Y�̎R�Ȃǂ���ǂ݉����Ă����B�C�M���X�ɗ��w�i���ƃu���X�g���j�������҂��C�C�M���X�l�̎��R�ς��C���j�╶�w���D������čl�@���Ă����B�P�Ȃ�C�M���X�̓c����^�ɏI����Ă��Ȃ��Ƃ���ɐV�N��������B
���u�C�M���X���l���v
����@�O�@���i��g���X�i�V���j�j��640
�@���҂͖����V���̃����h���x�ǒ��Ƃ��ĉp����15�N���؍݂����l�B�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẳs���ڂƁC�L�x�ȑ؉p�o���������G�b�Z�C�́C�}�S�̒��ȃG�b�Z�C�Ƃ͈�����悵�Ă���B������V�l���̂悤�Ȍ����b������グ�Ă��C�����ďd���Ȃ炸�C���m�ŁC�������f�l�ɂ�������₷�����������͓I�B
���u�p���f�f�v
�k���@�ā@���i�������_�V�Ёi���Ɂj�j��743
�@���҂́u���p��g�v�Ƃ������l���̌��l�Ƃ��ĉp���ɂQ�N�]��؍݂����l�B�b��́C�G���U�x�X�������͂��߂Ƃ��鉤���C�M���̖ʁX�C�p���O���ȂȂǁC��ʐl�ɂ͉��̂Ȃ��_�̏�̘b�肪�����̂͒��҂̗����d���Ȃ����C�p����ᔻ�I�Ɍ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��d���̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B�L���ێq���p���Ɋւ���G�b�Z�C����������ɁC����炢�͂���Ɓu�̂��l�v�̏����G�b�Z�C�������Ă��������낤�B�������C���{�l�����̉p����炵�ɂ͂قƂ�ǖ��ɗ����܂��B
���u���u���L�b�X�p���v
����~�J�@���i���ԕ��Ɂj��533

�@���҂́u�T�f�B�X�e�B�b�N�E�~�J�E�o���h�v�̃��H�[�J���X�g�Ƃ��Ĉꐢ���r�����l�c�Ƃ����Ύv���o���l�������낤�B�ޏ����u�p���A�b�p�[�~�h���N���X�̉Ƃ̉Łv�ɓ���C�p���l�̋`�ꂩ��O��I�ɉp�����̃��C�t�X�^�C���C���ɗ������w�ԁB�����ɂ̓��f�B�E�V�F�t�E�~�J�̉₩�ȃ��T�s27���t���Ă���B
���u�p���������T�@�����Ղ͏t���ɏ���āv
�o���ەv�@���E�C���X�g�i�������Ɂj��660
�@���̖{��ǂ�Ŏ�������s���Ă݂����Ǝv���̂́CStratford-upon-Avon��4��23���̃V�F�C�N�X�s�A�̒a�����ɍs����t�F�X�e�B�o���ł���B���̎����ɉp����K��邱�Ƃ͓�����炱����x�s���Ă݂����B�u�Ă̓p���_�C�X�v�Ƃ����G�b�Z�C�ŁC�u�w����k�̉ċx�݂��C������O�����͂����Ղ肠��B��������{�̂悤�ɏ����ĕ��ǂ���ł͂Ȃ�����x�ނƂ����̂ł͂Ȃ��āC�G�߂����܂�ɂ����������K������x�ނ̂ł���B�c�v�Əq�ׂ��Ă���B����́C���������Ƃ����{�����B�������ɂƂ��Ă��C�p���̉Ă͉������Ă��i���Ȃ��Ă��j�y�������K�ȋG�߂������B�������C�o�����̉p���т����������܂ł���Ƃ�����Ɓc�Ƃ������̂Ɂu�X�����̃f�U�[�g�v������B�u�f�U�[�g�͐��m�X�����̃N���[�������������B�i�V����ɃN���[���������ĐH�ׂ�K���͂������{�l�ɂ͂Ȃ����C���ۂɂ͂����Ԃ�����ł���B�D�݂̖�肾���C�i�V�ɂ̓`���R���[�g���������ق����悢�B�v�Əo�����͏q�ׂĂ���̂����C�F����͂ǂ��v���邾�낤���H
���u�p���������U�@�g���̂��镗�i�v
�o���ەv�@���E�C���X�g�i�������Ɂj��660
�@�U�̕��͉p���̐H�ƍg���Ɋւ���b�肪�����B�P�N�ԃo�[�X�ɕ�炵�Ă݂āC�E���E���������邱�Ƃ����邵�C��������������Ȃ邱�Ƃ�����B�u�����Ƌ����̐��͈��|�I�ɑO�҂̂ق�����������ǁC�����X��ɍs�ł���̂͋����ł���B�v�Əo�����͌������C�o�[�X�ňꌬ�����Ȃ������͎��̂悢���������Ă����ɂ�������炸�C�s�ł��Ă������߂��͂Ȃ��B�܂��C�u�C�M���X�̓������ŁC�����̗r�����������\�����������C�ŋ߂̌X���Ƃ��ẮC�^�[�L�[�Ƃ��O�[�X�Ƃ��`�L���ȂǁC������������ŐH�ׂ�K��������B�v�Ƃ̋L�q�����邪�C���̊��z�ł́C�����̃����i�Ƃ��ɏt��̃E�F�[���Y�Y�j�́C�u���\�v�łȂ��C�ނ��닍����肸���Ƃ��������B�܂��p���l�ɕ����Ă��C�`�L���͂Ƃ������C�O�[�X�͎��b�������ifatty�j�̂ŁC�H�ׂ�l�͍ŋߌ����Ă���B���ہC�N���X�}�X�O�ł����X�[�p�[�ł͂��܂茩�����Ȃ��B������C�C�M���X�̃p�u�ŃT�����[�}������������̂́u�V�F�p�[�Y�E�p�C�v���u�L�h�j�[�E�p�C�v�Ƃ����L�q�����邪�C�ǂ��̃p�u�̂��Ƃ��낤�H���Ȃ��Ƃ������g�͂��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��̂����B������菑�������C��������ł���G�b�Z�C�����邵�C���҂̃C���X�g����������B138�y�[�W�̖��̂���}�G��St Michael's Mount�ł��낤�B
���u�C�M���X�Ύ��L�v
�}�[�N�X���q�@���i�u�k�Ёj��1,456
�@���{�ŃC�M���X�т������\����G�b�Z�C�X�g�Ƃ����C�j���ł͌��킸�ƒm�ꂽ�����{�E�搶�C�����ł͂��̃}�[�N�X���q���ł��낤�B���������Ƃ͂����C�}�[�N�X���X�y���T�[����ŋM���̃}�[�N�X���ƌ������C�M���ƂȂ������ł��邩��C�������K�w�����������C�l�������ێ�I�i�p���l�����H�j�Ȃ̂͒v�����Ȃ��B�{���͒P�s�{�Ƃ��Ă͂���1993�N�Ɋ��s���ꂽ���C���̎��_�ł̏��l�������Ƃ��Ă��C�u�W���@�g�����v�̃L���O�ƃN�C�[���v�ʼn�����O��I�ɗi�삵�C�̃_�C�A�i�܂�O��I�ɔᔻ���Ă���̂ɂ́C�Ƃ��Ƀ_�C�A�i�t�@���ł͂Ȃ����ł���a�����o����B�`���[���Y�c���q�̕s�i�s�ɂ��Ă͉����G����Ă��Ȃ��̂��B�ѐM�ᎁ���}�[�N�X���q����]���āu��r�̈Ӗ���m��ʋM���̉����v�ƌ������̂́C�L�c�C�悤������ʂœI���˂Ă���B
���u�C�M���X���������Ȑ������v
�}�[�N�X���q�@���i�������Ɂj��667
�@�^�C�g�����炠����x�z�������悤�ɁC�t�@�b�V�����̘b��ł��Ȃ�̃y�[�W���g���Ă���B���́C�t�@�b�V�����͂قƂ�NJS���Ȃ��̂Ńs���Ƃ��Ȃ������B�_�C�A�i���̎����O�̃G�b�Z�C�u�_�C�A�i�܂̔����v�ŁC���ς�炸�_�C�A�i�܂������ɂ߂Ĕl��C�`���[���Y�c���q�������Ă���̂�ǂނƁC�}�[�N�X���q���͉p������������{���킳�ꂽ�ҁH�Ƃ��������Ă��܂��B
���u�����C�M���X�ɕ�炷�킽���v
��`�c�q�@���i�����ܕ��Ɂj��600
�@�ҏW�ҁC���W�I��DJ�ȂǖZ���������𑗂�Ȃ���C�S�̃I�A�V�X�Ƃ��Ă����p���̂��Ƃ�Y��Ȃ��Ƃ������҂̃G�b�Z�C�͂��łɑ����o�Ă��邩��C���̖���m���Ă���l���������낤�B�u����v�������Ă���u�C�M���X��^�{�v�匙���̗ѐM�ᎁ�����E���邾�������āC�C�M���X���x�^�_�߂��邱�ƂȂ��ɁC�Ȃ�����Ȃɂ����̍��Ɏ䂩���̂��Ƃ����S��W�X�ƌ���Ă���B�m�����D�~�����ɃC�M���X�����Ƃ�����ю��̋������Ă̂�������Ȃ��B�������C���̔��ʁC�J��Ԃ��ǂ݂����Ȃ�悤�Ȏ�������G�b�Z�C�Ƃ��������̂���͉����āC�����ЂƂnj㊴�������B����݂ɂȂ炸�C�������ʔ����G�b�Z�C���������Ƃ������ɓ�����悭�킩��B
���u�p���ɏA�āv
�g�c����@���i�����ܕ��Ɂj��620
�@�ɑ��g�c�̎q���ɂ��āC�p���т����̑������I���݂ł���g�c����1974�N�ɒ������ÓT�I���G�b�Z�C�B���̃G�b�Z�C�������ꂽ���Ƃ͉p�������{���傫���ς�������낤���C�g�c���̕��̂ɂ��Â߂������Ƃ��낪���邪�C���ǂ�ł��ʔ����̂́C�g�c�������N���ォ��t����ɂ����ĉp���ŋ�����C�p���̓`���������������R�ɐg�ɂ���Ƃ����H�Ȍo����ς���ł��낤�B
���u�p����������萶���p�v
�я����Y�@���i�������Ɂj��620
�@�����]�_�Ƃł��钘�҂��u���e�B�b�V���E�g���f�B�V���i���E�t�@�b�V�����ƃJ���g���[�T�C�h�I�s����Șb��Ƃ��ĒԂ����������ȃG�b�Z�C�B�`���[�`���̈������t�@�b�V������n�o�i�V�K�[�̃G�s�\�[�h���ʔ����B������C���O�����h�̏����Ȓ������W�[�ɂ����u�u���[�h�����Y�̊فv��K�ꂽ�̂́C���̃G�b�Z�C��ǂ̂����������������B
���u�p���l�G�̍ʂ�v
�я����Y�@���i�������Ɂj��640
�@1998�N�̒��Ҏ����̔��N��ɏo�ł��ꂽ�G�b�Z�C�B�J���[�łȂ��̂��c�O�����C���Ҏ��g���`�������̂���C���X�g���Y�����Ă���B�J���g���[�T�C�h�I�s�����S�����C���ʒ������ꏊ��K��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������C�����ɂ͂��Ƃ�����Ƃ��낪���鎠���L���ȃG�b�Z�C���B
 �@�@
�@�@